4年に1度訪れる特別な年、「うるう年」。次のうるう年はいつかしら、と気になりますね。うるう年は、私たちが使う暦と実際の季節がずれてしまわないよう、地球の周期に合わせて調整するための大切な仕組みです。この記事を読めば、うるう年の意味や計算方法、2月29日生まれの方の誕生日がどうなるかといった疑問まですっきりと解決します。暮らしの中の暦の不思議を、一緒に紐解いてみませんか。

1. うるう年とは4年に1度2月29日がある年のこと
毎日めくるカレンダー、眺めていると「あれ?」と思う年がありませんか。2月が28日までではなく、29日まである年。それが「うるう年(閏年)」です。なんだか少し得したような、特別な気持ちになる日ですよね。
うるう年とは、ふだんは365日の1年が、366日になる年のこと。4年に1度のペースでやってきて、2月に「29日」が加えられます。この追加された1日を「うるう日(閏日)」と呼びます。
私たちの暮らしに身近なこの「うるう年」ですが、なぜこのような調整が必要なのでしょうか。この記事では、そんな素朴な疑問から、誕生日が2月29日の方はどうなるの?といった気になる話題まで、わかりやすく紐解いていきます。
1.1 2024年の次はいつ?未来のうるう年
この記事を読んでいらっしゃる2024年は、まさにうるう年です。オリンピック・パラリンピックが開催された年として、記憶にも新しいかもしれませんね。
では、この次のうるう年はいつになるのでしょうか。基本的には4年後ですので、2024年の次のうるう年は、4年後の2028年となります。その先も、4年ごとにうるう年が訪れますよ。
今後のうるう年を、少し先まで一覧にしてみました。ご自身の年齢や、ご家族の記念日などと重ねながら眺めてみるのも楽しいかもしれませんね。
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2024年 | 令和6年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2032年 | 令和14年 |
| 2036年 | 令和18年 |
| 2040年 | 令和22年 |
このように、基本的には西暦の年数が「4」で割り切れる年がうるう年となります。ただし、実は簡単な割り算だけでは決まらない、少し複雑なルールも隠されています。その詳しい計算方法については、後の章でゆっくりとご説明しますね。
2. うるう年がなぜ必要かその理由をわかりやすく解説
4年に1度めぐってくる、うるう年。カレンダーに「2月29日」が現れる特別な年ですが、なぜこのような調整が必要なのでしょうか。その背景には、私たちの暮らしに欠かせない「季節」を守るための、古くからの知恵が隠されているのですよ。
2.1 地球の公転周期と暦のずれを調整するため
私たちが普段使っているカレンダーでは、1年は「365日」とされていますね。しかし、地球が太陽の周りをひとまわりするのにかかる時間(公転周期)は、正確には約365.2422日なのです。ほんのわずかな差に思えるかもしれませんが、この「約0.2422日」というずれが、実はとても重要です。
1年で約0.2422日、時間にすると約6時間のずれは、何もしないでいると毎年少しずつ積み重なっていきます。その様子を少し見てみましょう。
| 経過年数 | 暦と実際の季節とのずれ |
|---|---|
| 1年後 | 約6時間 |
| 2年後 | 約12時間 |
| 3年後 | 約18時間 |
| 4年後 | 約24時間(ほぼ1日) |
このように、4年が経つ頃には、暦と地球の実際の位置が約1日もずれてしまいます。このずれを解消するために、4年に1度「うるう日(2月29日)」を加えて、暦の帳尻を合わせているのです。うるう年は、私たちのカレンダーを地球の動きにぴったりと合わせるための、大切な「調整日」というわけですね。
より詳しい情報については、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。
2.2 もしうるう年がなかったら季節はどうなるか
では、もしこの「うるう年」という仕組みがなかったら、私たちの暮らしはどうなってしまうのでしょうか。
毎年約6時間ずつ暦が季節より先に進んでいくと、長い年月をかけて大きな影響が出てきます。例えば、100年後には約25日もずれてしまいます。そうなると、暦の上では夏なのに、実際の気候はまだ春のまま…なんてことが起こってしまうのです。
さらに時が経てば、桜が咲く季節にお正月を迎えたり、真夏にコートが必要になったりするかもしれません。これでは、種まきや収穫の時期が大切な農業はもちろん、お花見や七夕、お祭りといった季節の行事も、本来の時期とは全く違うタイミングで行うことになってしまいます。
うるう年は、私たちが当たり前のように感じている「季節感」を守り、暦と暮らしがずれてしまわないようにするための、なくてはならない大切な仕組みなのですね。
3. うるう年の計算方法と400年に97回となるルール
「うるう年は4年に1度」と覚えていらっしゃる方が多いかもしれませんが、実はもう少しだけ詳しいルールがあるのですよ。少し複雑に聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。3つのステップで見ていくと、意外と簡単に理解できます。このルールがあるおかげで、私たちの使うカレンダーと地球の動きとの間の、ほんのわずかなズレが正確に調整されているのです。
この計算方法によって、うるう年は400年の間に97回やってくることになります。それでは、その仕組みを一緒に見ていきましょう。
3.1 原則1 西暦が4で割り切れる年
まず、基本となるのがこのルールです。テレビでオリンピックの話題がのぼる年を思い浮かべると、イメージしやすいかもしれませんね。
西暦の年数が4で割り切れる年は、原則として「うるう年」となります。例えば、2024年は4で割り切れるのでうるう年です。同じように、次の2028年、2032年もカレンダーに2月29日が登場します。
3.2 例外ルール1 西暦が100で割り切れる年は平年
原則だけですと、実は少しずつカレンダーがずれていってしまいます。そこで、最初の例外ルールが登場します。
西暦の年数が100で割り切れる年は、4で割り切れたとしても「平年(うるう年ではない)」になります。例えば、皆さまが経験された1900年は、4でも100でも割り切れるため、このルールが適用されて平年でした。これから先ですと、2100年が同じように平年となります。
3.3 例外ルール2 西暦が400で割り切れる年はうるう年
例外ルールがもう一つだけあります。これで計算の仕上げです。
西暦の年数が100で割り切れる年の中でも、さらに400でも割り切れる場合は、特別に「うるう年」となります。記憶に新しい2000年が、ちょうどこの年にあたります。2000年は100で割り切れますが、同時に400でも割り切れるため、うるう年として2月29日がありました。次にこのルールが適用されるのは、2400年です。
これらの3つのルールをまとめると、次のようになります。
| ルール | 条件 | 判定 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 西暦が4で割り切れる | うるう年 | 2024年, 2028年 |
| 例外1 | 西暦が100で割り切れる | 平年 | 1900年, 2100年 |
| 例外2 | 例外1のうち、西暦が400で割り切れる | うるう年 | 2000年, 2400年 |
この仕組みは「グレゴリオ暦」という現在世界中で使われている暦のルールに基づいています。より詳しい情報については、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。
4. うるう年の一覧 過去と未来
「次のうるう年はいつかしら?」と気になったり、「あの年はうるう年だったのね」と過去を振り返ったり。ここでは、私たちが生きる21世紀のうるう年から、少し昔の明治時代まで、うるう年を一覧でご紹介します。カレンダーを眺めながら、ご自身の人生の節目と重ね合わせてみるのも楽しいかもしれませんね。
4.1 21世紀のうるう年一覧(2001年から2100年)
まずは、現在私たちが過ごしている21世紀(2001年〜2100年)のうるう年を見ていきましょう。平成から令和へと時代が移り変わる中で、たくさんのうるう年がありました。未来のうるう年も、こうして見ると意外とすぐにやってくるのですね。
ひとつ覚えておきたいのが、2100年は、うるう年ではないということです。これは「西暦が100で割り切れる年は平年」という例外ルールが適用されるため。ちょっとした豆知識として覚えておくと、誰かにお話しできるかもしれません。
| 西暦(和暦) | 西暦(和暦) | 西暦(和暦) | 西暦(和暦) |
|---|---|---|---|
| 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
| 2020年(令和2年) | 2024年(令和6年) | 2028年(令和10年) | 2032年(令和14年) |
| 2036年(令和18年) | 2040年(令和22年) | 2044年(令和26年) | 2048年(令和30年) |
| 2052年(令和34年) | 2056年(令和38年) | 2060年(令和42年) | 2064年(令和46年) |
| 2068年(令和50年) | 2072年(令和54年) | 2076年(令和58年) | 2080年(令和62年) |
| 2084年(令和66年) | 2088年(令和70年) | 2092年(令和74年) | 2096年(令和78年) |
4.2 明治から昭和までのうるう年
続いて、明治、大正、昭和の時代にあったうるう年を振り返ってみましょう。日本で現在使われている暦(グレゴリオ暦)は、明治6年(1873年)から始まりました。ご自身の生まれた年や、ご両親、おじいさま、おばあさまの思い出の年を探してみるのも素敵ですね。
ここでもひとつ、面白い発見があります。明治33年(1900年)は、うるう年ではありませんでした。これも2100年と同じで、「100で割り切れる年は平年」というルールが適用されたためです。歴史の中にも、暦の正確なルールが息づいているのですね。
| 元号 | うるう年(西暦) |
|---|---|
| 明治 | 1876年, 1880年, 1884年, 1888年, 1892年, 1896年, 1904年, 1908年 |
| 大正 | 1912年, 1916年, 1920年, 1924年 |
| 昭和 | 1928年, 1932年, 1936年, 1940年, 1944年, 1948年, 1952年, 1956年, 1960年, 1964年, 1968年, 1972年, 1976年, 1980年, 1984年, 1988年 |
より詳しい情報や暦の計算については、国立天文台の情報も参考になります。
参考:うるう年とは – 暦Wiki/うるう年 – 国立天文台暦計算室
5. 2月29日生まれの誕生日はどうなる?年齢の数え方や法律上の扱い
4年に1度しか訪れない、2月29日。この特別な日にお生まれになった方は、ご自身の誕生日をどのように過ごされているのでしょうか。お祝いはいつするのか、そして法律の上では年齢をどのように数えるのか、気になる方も多いことでしょう。ここでは、2月29日生まれの方の誕生日にまつわる様々な疑問について、一つひとつ丁寧にご案内いたします。
5.1 法律上の誕生日は2月28日として扱われる
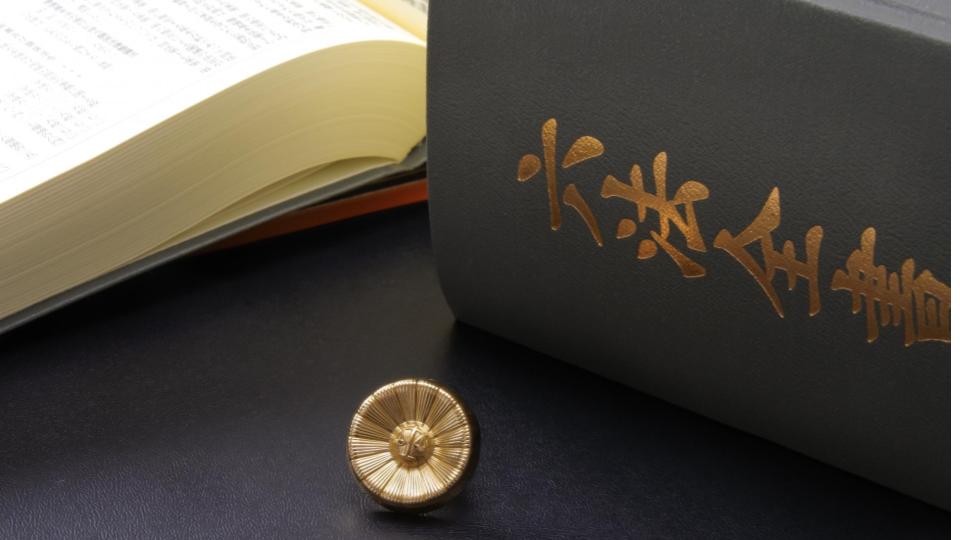
「誕生日が来ない年は、年を取らないの?」なんて冗談を耳にすることもありますが、もちろんそんなことはありません。法律では、うるう年ではない平年において、2月29日生まれの方の誕生日は「2月28日」とみなされます。そのため、他の日と同じように、毎年きちんと年齢を重ねていきますのでご安心くださいね。では、なぜそのように決められているのでしょうか。その背景には、年齢の数え方に関する国の法律が関係しています。
5.1.1 民法における年齢計算の規定
年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」および「民法」という法律で定められています。少し難しく聞こえるかもしれませんが、仕組みはとてもシンプルです。
これらの法律を要約すると、「人は、誕生日の前日が満了する時(午後12時)をもって、満年齢に達する」と解釈されています。例えば、4月10日生まれの人は、その前日である4月9日の午後12時が終わる瞬間に1つ年を取る、ということになります。
このルールを2月29日生まれの方にあてはめてみましょう。うるう年ではない平年では2月29日が存在しないため、その「前日」にあたる日は2月28日となります。したがって、2月28日の午後12時が終わる瞬間に、満年齢が1つ加算されるのです。こうした理由から、法律上は2月28日が誕生日として扱われるのですね。
5.2 運転免許証の更新や手続きについて
暮らしに身近な運転免許証の更新手続きも、この法律上の考え方が基本となります。免許証の更新期間は「誕生日の1か月前から1か月後まで」ですが、2月29日生まれの方はどうなるのでしょうか。
この場合も、うるう年以外の年は2月28日を誕生日とみなして、更新期間が設定されます。つまり、更新期間は「1月28日から3月28日まで」となります。2月29日がない年でも、免許の更新ができないといった不利益が生じることはありませんので、ご安心ください。
この考え方は、運転免許証だけでなく、パスポートの申請や各種保険の手続き、年金の受給開始年齢など、年齢が関わる多くの公的な手続きで同様に適用されています。
5.3 誕生日のお祝いはいつする?
法律上の扱いは決まっていますが、ご家族やご友人と過ごす誕生日のお祝いは、また別の話ですよね。いつお祝いするかに厳密なルールはありません。ご本人やご家族が「この日がいいな」と思える日を選ぶのが一番素敵です。一般的には、いくつかのパターンがあるようです。
| お祝いする日 | 主な理由や考え方 |
|---|---|
| 2月28日 | 法律上、年を重ねる日である「誕生日の前日」としてお祝いする考え方です。「前祝い」のような気持ちで楽しむ方が多いようです。 |
| 3月1日 | 「2月の最終日の次」という意味で、3月1日にお祝いする考え方です。こちらの方がしっくりくる、という方もいらっしゃいます。 |
| 2月28日と3月1日の両日 | 28日に前夜祭、1日に本祝いといった形で、2日間にわたってお祝いを楽しむ、なんとも贅沢な過ごし方です。 |
| うるう年に盛大にお祝い | 4年に1度の「本当の誕生日」は特別に盛大なお祝いをして、他の年はささやかにお祝いするというメリハリのある楽しみ方です。 |
どの日にしても、大切なのは「生まれてきてくれてありがとう」という祝福の気持ち。4年に1度という特別な日に生まれたからこそ、お祝いの仕方を自由に選べるのも、一つの楽しみ方かもしれませんね。
6. うるう年に関するよくある質問や豆知識

4年に1度めぐってくる「うるう年」。なんだか少し特別な感じがしますよね。ここでは、うるう年にまつわる素朴な疑問や、知っているとちょっと誰かに話したくなるような豆知識をご紹介します。日々の暮らしに彩りを添える、ささやかな話題を見つけてみませんか。
6.1 うるう秒やうるう月との違いとは
「うるう」と聞くと、「うるう秒」という言葉を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんね。名前は似ていますが、「うるう年」と「うるう秒」は全く別のものです。また、昔使われていた暦には「うるう月」というものもありました。それぞれの違いを簡単にまとめてみましょう。
| 種類 | 調整するもの | 調整方法 | 目的 |
|---|---|---|---|
| うるう年 | 暦(太陽暦) | 約4年に1度、2月29日を1日追加する | 地球が太陽の周りを回る周期(季節)と暦のずれを合わせるため |
| うるう秒 | 時刻(世界標準時) | 数年に1度、1秒を追加または削除する | 地球の自転の速さのずれと時刻を合わせるため |
| うるう月 | 旧暦(太陰太陽暦) | 約3年に1度、1ヶ月を追加する | 月の満ち欠けを基準にした暦と季節のずれを合わせるため |
このように、うるう年は「季節」と「暦」のずれ、うるう秒は「時間」と「地球の自転」のずれを調整するもので、目的が異なります。ちなみに、「うるう秒」による調整は、情報通信システムなどへの影響が大きいことから、2035年までに廃止されることが国際的に決まっています。時代の流れとともに、暦や時間の仕組みも少しずつ変わっていくのですね。
6.2 オリンピックはうるう年に開催される?
「オリンピックはうるう年に開かれる」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。確かに、近代オリンピックが始まってから、夏の大会はうるう年に開催されるのが慣例となっていました。
例えば、最近の大会を振り返ってみても、
- 2024年 パリ大会
- 2020年 東京大会(※もともとの開催予定年)
- 2016年 リオデジャネイロ大会
- 2012年 ロンドン大会
と、うるう年が並びます。これは、第1回のアテネ大会が1896年(うるう年)に行われたことに由来するそうです。
しかし、これはあくまで慣例であり、必ずしも「夏季オリンピック=うるう年」という決まりがあるわけではありません。記憶に新しい2020年の東京オリンピックは、世界的な事情で1年延期され、2021年に開催されました。これも、ルールではないからこそできた対応と言えるでしょう。
ちなみに、冬季オリンピックは、うるう年とその次のうるう年の中間の年(西暦を4で割ると2余る年。2022年、2026年など)に開催されています。夏と冬、それぞれが2年ごとに楽しめるようになっているのですね。
6.3 うるう年の歴史とグレゴリオ暦
私たちが今、当たり前のように使っている「うるう年」の仕組みは、長い歴史の中で人々の知恵によって作られてきました。その物語は、古代ローマ時代にまでさかのぼります。
もともと、うるう年の考え方を最初に取り入れたのは、古代ローマの英雄ユリウス・カエサルが定めた「ユリウス暦」でした。ここでは「4年に1度、1日を追加する」というシンプルなルールが採用されました。
しかし、この方法では、実際の地球の公転周期(約365.2422日)との間に、わずかなずれが生まれてしまいます。1年で約11分のずれは、100年、200年と経つうちにどんどん大きくなり、16世紀には暦と季節が10日以上もずれてしまう事態になりました。
このずれを解消するために、1582年にローマ教皇グレゴリウス13世が新しい暦を導入しました。これが、現在私たちが使っている「グレゴリオ暦」です。グレゴリオ暦では、ユリウス暦のルールに加え、
- 西暦が100で割り切れる年は、うるう年にしない(平年とする)
- ただし、400で割り切れる年は、うるう年にする
という、より精密なルールを設けました。このおかげで、暦と季節のずれが大幅に小さくなり、より正確な暦が実現したのです。うるう年は、天体の動きを正確に捉えようとした、先人たちの長い努力の結晶なのですね。この暦の歴史について、より詳しくは国立天文台の暦Wikiでも解説されています。
7. まとめ
うるう年について、その意味や理由、少し複雑な計算方法までご紹介しました。4年に一度めぐってくる2月29日は、地球の公転と暦のズレを調整するための、暮らしに欠かせない知恵なのですね。このおかげで、私たちは毎年同じ時期に季節の移ろいを感じることができます。2月29日生まれの方の誕生日など、特別な日ならではのルールも興味深いもの。次のうるう年を心待ちにしながら、暦の奥深さに思いを馳せてみるのも素敵ですね。

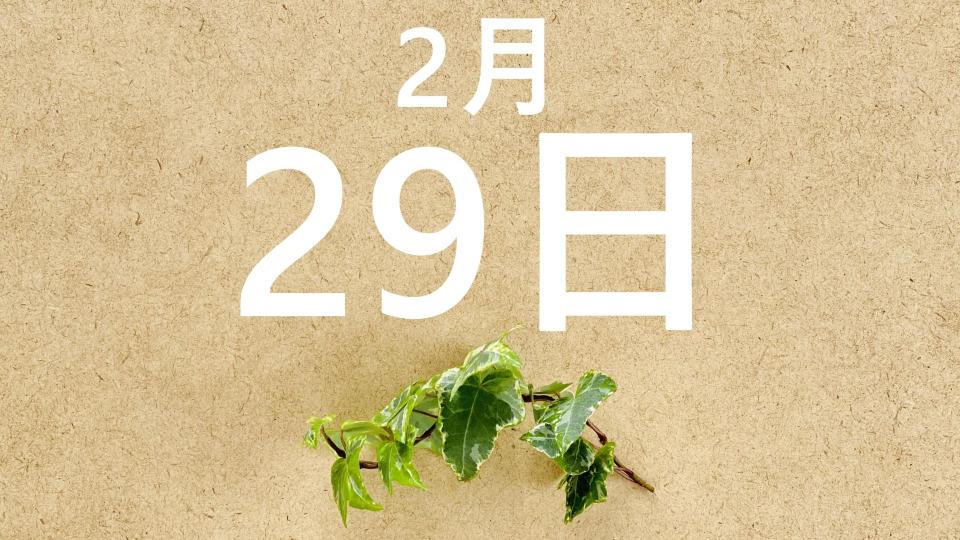








コメント