新しい年が始まり、大切な方へのご挨拶の機会が増える1月。あらたまったお手紙から気軽なメッセージまで、どんな言葉を選べば良いか迷うこともありますね。この記事では、ビジネスやプライベートですぐに使える1月の挨拶文例を、時期や相手別に詳しくご紹介します。松の内を過ぎた場合や寒中見舞いのマナーもわかるので安心。あなたらしい、心のこもった言葉選びのお手伝いをします。

1. 1月の挨拶で押さえておきたい時候の言葉と時期

新しい年が始まる1月は、お世話になっている方へ挨拶をする機会が多い特別な月ですね。手紙やメールを送る際、季節感を表す「時候の挨拶」を添えることで、ぐっと心のこもった丁寧な印象になります。
ひとくちに1月といっても、お正月気分が華やぐ上旬、寒さが本格化する中旬、そして一年で最も冷え込む下旬と、季節の表情は少しずつ移り変わります。その時々にふさわしい言葉を選ぶことで、相手を気遣う気持ちがより深く伝わりますよ。ここでは、1月を上旬・中旬・下旬に分けて、それぞれの時期にぴったりの時候の言葉をご紹介します。
1.1 1月上旬(松の内まで)に使える挨拶
年が明けてからお正月の松飾りが飾られている期間を「松の内(まつのうち)」と呼びます。この期間は、新年を寿ぐ(ことほぐ)華やかな言葉を選ぶのが習わしです。一般的に、松の内は関東では1月7日まで、関西では1月15日までとされることが多いようです。お相手の住む地域に合わせられると、より丁寧な心遣いが伝わりますね。
この時期には、「新しい春」を意味する「新春」や「初春」といった言葉がよく使われます。
| 時候の言葉 | 読み方 | 意味・使える時期 |
|---|---|---|
| 新春の候 | しんしゅんのこう | 新しい年、新しい春を迎えた季節。松の内(1月7日頃まで)に使うのが一般的です。 |
| 初春の候 | しょしゅんのこう | 春の初め。暦の上では立春(2月4日頃)までが春の初めですが、主に松の内に使います。 |
| 迎春の候 | げいしゅんのこう | 新しい春を迎えた喜びを表す言葉。こちらも松の内に使うのがふさわしいです。 |
| 年始の候 | ねんしのこう | 年の初め。松の内はもちろん、1月中旬頃まで使うことができます。 |
文頭に「謹んで新春のお慶びを申し上げます。」といったお祝いの言葉(賀詞)を添えてから、時候の挨拶につなげると、より改まった印象になります。
1.2 1月中旬に使える挨拶
松の内が明ける1月中旬頃は、お正月気分も落ち着き、寒さが本格化してくる季節です。二十四節気の「小寒(しょうかん)」を過ぎ、「寒の入り」とも呼ばれるこの時期には、寒さの厳しさを表す言葉が時候の挨拶として使われます。
寒さの中にも、相手の健康を気遣う一言を添えることで、温かい気持ちが伝わります。
| 時候の言葉 | 読み方 | 意味・使える時期 |
|---|---|---|
| 小寒の候 | しょうかんのこう | 寒さが一段と厳しくなる頃。小寒(1月5日頃)から大寒(1月20日頃)までの期間に使います。 |
| 寒冷の候 | かんれいのこう | 寒く冷たい気候の頃。1月中旬から下旬にかけて幅広く使えます。 |
| 寒の入り | かんのいり | 「寒の入りを迎え、いよいよ冬本番となりましたが」のように、書き出しの言葉として使えます。 |
「寒さ厳しき折」「めっきり寒くなりましたが」といった表現も、この時期の挨拶にぴったりです。年賀状ではなく、通常の挨拶状として送る「寒中見舞い」を出し始めるのもこの頃からですね。
1.3 1月下旬(大寒の頃)に使える挨拶
1月20日頃からは、二十四節気の最後の節気である「大寒(だいかん)」を迎えます。その名の通り、一年で最も寒さが厳しくなる時期です。時候の挨拶も、その厳しい寒さを表現する言葉が中心となります。
冷え込みが厳しい毎日だからこそ、挨拶の言葉に温かみを添えたいもの。厳しい寒さの中にも、ふと見つかる春の兆しに触れると、前向きで明るい印象の文章になりますよ。
| 時候の言葉 | 読み方 | 意味・使える時期 |
|---|---|---|
| 大寒の候 | だいかんのこう | 一年で最も寒い頃。大寒(1月20日頃)から立春(2月4日頃)の前日まで使えます。 |
| 厳寒の候 | げんかんのこう | 厳しい寒さの季節。1月下旬から2月上旬にかけて使うのに適しています。 |
| 酷寒の候 | こっかんのこう | きわめて厳しい寒さを表す言葉。「厳寒」よりもさらに強い寒さを表現します。 |
例えば、「大寒のみぎり、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」といった改まった表現のほか、「寒さの中にも、梅の蕾がふくらみ始め、春の訪れが待ち遠しい今日この頃です。」のように、季節の情景を織り交ぜるのも素敵ですね。
2. 【ビジネス】フォーマルな1月の挨拶例文

新しい年の始まりは、お仕事でお世話になっている方々へ心を込めて挨拶を伝えたいものですね。特に1月は、年始の挨拶が今後の関係性をより良いものにする大切な機会となります。ここでは、ビジネスシーンで使えるフォーマルな挨拶を、メールと手紙に分けてご紹介します。少しの違いで印象がぐっと良くなる、そんな言葉選びのヒントを見つけてみてくださいね。
2.1 メールの書き出しで使える1月の挨拶
ビジネスメールでは、まず件名で「新年のご挨拶」であることが分かるようにしましょう。本文の書き出しは、賀詞(お祝いの言葉)と、日頃の感謝や相手を気遣う一文を組み合わせるのが基本です。松の内(一般的に1月7日、地域によっては15日まで)を過ぎたら、「あけましておめでとうございます」という直接的な表現は控え、「本年もよろしくお願いいたします」から始めると丁寧ですよ。
使いやすい書き出しのフレーズをいくつかご紹介します。
| 時期 | 挨拶の文例 |
|---|---|
| 松の内まで | 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。 |
| 松の内まで | 新年おめでとうございます。 昨年は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。 |
| 松の内以降 | 寒さ厳しき折、〇〇様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 |
| 松の内以降 | 寒の入りを迎え、本格的な冬の到来となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 |
「謹賀新年」や「恭賀新年」といった4文字の賀詞は、目上の方にも使える丁寧な表現ですが、メールでは少し堅い印象になることも。相手との関係性に合わせて「謹んで新春のお慶びを申し上げます」のように文章で表現すると、より柔らかく気持ちが伝わります。
2.2 メールの結びに使える1月の挨拶
メールの結びは、相手の健康や会社の発展を願う言葉で締めくくるのが一般的です。新しい年への期待が感じられるような、前向きな言葉を選ぶと良いでしょう。相手や状況に合わせて、心遣いの伝わる一言を添えてみましょう。
| 相手 | 結びの文例 |
|---|---|
| 取引先など社外の方へ | 本年も変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| 取引先など社外の方へ | 貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 上司など社内の方へ | 本年もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
| 共通して使える言葉 | 寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。 |
| 共通して使える言葉 | 〇〇様にとって幸多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。 |
結びの言葉の前に、「まずは、新年のご挨拶まで。」といった一文を添えると、メールの目的が挨拶であることを示し、丁寧な印象になりますよ。
2.3 手紙で使える改まった1月の挨拶
より丁寧な気持ちを伝えたいときや、特に重要なお取引先、お世話になった恩師などへは、手紙で挨拶状を送るのも素敵ですね。手紙では「拝啓」で始まり「敬具」で結ぶといった、基本の形式を大切にしましょう。時候の挨拶から始まり、感謝の言葉、そして今後の変わらぬお付き合いをお願いする気持ちを綴ります。
2.3.1 取引先向けの文例
取引先へ送る手紙では、日頃の感謝と共に、相手企業の繁栄を願う気持ちを伝えることが大切です。旧年中の感謝を具体的に述べると、より心のこもった手紙になります。
【文例】
拝啓
新春の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで、弊社も無事に新しい年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の温かいご支援の賜物と深く感謝しております。
本年も、より一層お役に立てるよう社員一同精一杯努めてまいる所存でございますので、昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具
2.3.2 上司向けの文例
お世話になっている上司への手紙では、指導への感謝と、新年の抱負を伝えることで、仕事への意欲を示すことができます。個人的な健康を気遣う一文を添えると、温かみのある手紙になります。
【文例】
拝啓
初春の候、〇〇(上司の氏名)様におかれましては、ご健勝にて新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
旧年中は、公私にわたり大変お世話になりました。特に〇〇の件では、未熟な私を熱心にご指導いただき、誠にありがとうございました。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
気持ちを新たに、今年は〇〇を目標に掲げ、少しでも部署に貢献できるよう精進してまいります。
寒さ厳しき折、くれぐれもご無理なさらないでください。
〇〇様とご家族の皆様にとりまして、幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。
敬具
3. 【プライベート】カジュアルな1月の挨拶例文

気心の知れたご友人や親しい方との挨拶は、ビジネスシーンほど形式にこだわる必要はありません。とはいえ、新しい年の始まりには、やはり心を込めた言葉を交わしたいものですね。ここでは、メールやLINE、年賀状の返信など、さまざまな場面で使えるカジュアルな挨拶の文例をご紹介します。あなたらしい言葉を添えて、大切な方へ新年の気持ちを伝えてみませんか。
3.1 友人へのメールやLINEで使える1月の挨拶
メールやLINEでの新年のご挨拶は、手軽ながらも温かい気持ちを伝える素敵な方法です。定番のフレーズに、相手の健康を気遣う一言や、次への期待が膨らむような言葉を添えるだけで、ぐっと心のこもったメッセージになりますよ。
| シーン | 例文 |
|---|---|
| 定番のシンプルな挨拶 | あけましておめでとう! 昨年はたくさんお世話になりました。 なかなか会えないけれど、〇〇さんのことはいつも気にかけています。 今年が〇〇さんにとって、笑顔あふれる素敵な一年になりますように。 また近いうちに、ゆっくりお茶でもしましょうね。 |
| 近況を交えた挨拶 | 〇〇さん、Happy New Year! お正月はいかがお過ごしでしたか? 私は家族とのんびり過ごし、すっかりリフレッシュしました。 昨年は素敵なランチに連れて行ってくれてありがとう。とても楽しかったです。 また美味しいものを食べに行きましょうね。楽しみにしています! 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
| 少し会えていない友人への挨拶 | 〇〇ちゃん、新年あけましておめでとう。 ご無沙汰していますが、お元気にしていますか? 厳しい寒さが続いていますが、どうか温かくしてお過ごしくださいね。 今年はぜひお会いして、積もる話がたくさんしたいです。 また連絡しますね。今年もよろしくお願いします! |
3.2 年賀状の返信や年始の連絡に使える挨拶
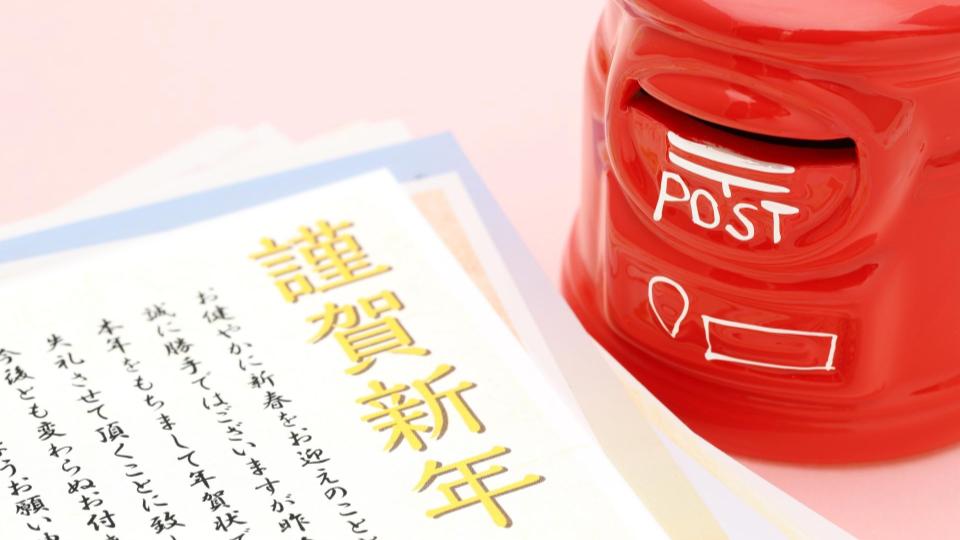
年賀状をいただいたものの、こちらから出していなかったり、喪中で控えたりした場合の返信には、少し配慮が必要です。返信する時期に合わせて、適切な言葉を選びましょう。お相手への感謝と、年始の挨拶が遅れたお詫びの気持ちを丁寧に伝えることが大切です。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 年賀状を出しそびれた相手への返信(松の内まで) | あけましておめでとうございます。 素敵な年賀状をありがとうございました。ご家族の皆様もお元気そうで何よりです。 年末から何かと忙しく、新年のご挨拶が遅れてしまい申し訳ありません。 昨年は大変お世話になりました。本年も変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。 |
| 年賀状をいただいた相手への返信(松の内を過ぎてから) | 寒中お見舞い申し上げます。 この度は、丁寧な年始のご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。 ご挨拶が遅れまして、大変失礼いたしました。 まだまだ寒い日が続きますが、〇〇さんもどうぞご自愛ください。 本年もよろしくお願い申し上げます。 |
| 喪中と知らずに年賀状をくださった方への返信 | 寒中お見舞い申し上げます。 年始のご挨拶をいただき、ありがとうございました。 昨年〇月に(続柄)が永眠いたしましたため、年末年始のご挨拶を控えさせていただきました。 ご連絡が行き届かず、大変申し訳ございません。 寒い日が続きますので、皆様どうぞご自愛ください。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
喪中の際の詳しいマナーについては、日本郵便のウェブサイトも参考になります。
喪中・年賀欠礼に関するQ&A – 日本郵便
4. 1月の挨拶に便利な「寒中見舞い」の基本

「うっかり年賀状を出しそびれてしまった…」「喪中の方へ、年始のご挨拶をしたいけれどどうすれば…」。そんな1月の挨拶のお悩みに、心強い味方となってくれるのが「寒中見舞い」です。寒中見舞いは、一年で最も寒さが厳しい時期に、相手の健康を気遣う季節の挨拶状。松の内を過ぎてしまった場合の年始の挨拶や、喪中の方へのご挨拶など、様々な場面で使うことができるのですよ。ここでは、いざという時に役立つ寒中見舞いの基本を、分かりやすくご紹介しますね。
4.1 寒中見舞いを出す時期はいつからいつまでか
寒中見舞いをいつ送ればよいのか、迷われる方も多いかもしれませんね。基本的には、年始の挨拶期間である「松の内」が明けてから、「立春」の前日までに相手に届くように送るのがマナーとされています。
少し注意したいのが、「松の内」の期間は地域によって異なるという点です。ご自身のお住まいの地域だけでなく、お相手の地域の習慣にも配慮できると、より丁寧な印象になりますよ。一般的な目安は、下の表を参考にしてみてくださいね。
| 地域 | 松の内の期間 | 寒中見舞いを出し始める時期 |
|---|---|---|
| 関東・東北・九州地方など | 1月1日~1月7日 | 1月8日頃から |
| 関西地方など | 1月1日~1月15日 | 1月16日頃から |
そして、寒中見舞いを送る期限は、暦の上で春が始まる「立春」の前日までです。立春は例年2月4日頃にあたります。もし立春を過ぎてしまった場合は、「寒中見舞い」ではなく「余寒見舞い」として、春が来てもまだ残る寒さについて相手を気遣うお便りを出すことができますよ。
4.2 寒中見舞いの書き方と文例
寒中見舞いには、基本的な構成があります。難しく考えずに、相手を思いやる気持ちを込めて、次のような流れで書いてみましょう。
- 季節の挨拶(決まり文句)
- 相手の安否を気遣う言葉
- ご自身の近況報告
- 結びの言葉
- 日付
ここで大切なポイントがいくつかあります。まず、寒中見舞いには年賀はがきは使いません。普通の官製はがきや、季節の花が描かれた私製はがきなどを使うようにしましょう。また、「拝啓」や「敬具」といった頭語・結語は不要です。
それでは、具体的な文例をいくつか見ていきましょう。
4.2.1 年賀状の返信が遅れてしまった場合の文例
寒中お見舞い申し上げます。
この度は、心のこもったお年賀状をいただき、誠にありがとうございました。
年末年始は何かと慌ただしくしており、ご挨拶が遅れてしまい大変失礼いたしました。
厳しい寒さが続いておりますが、〇〇様もご家族の皆様も、どうぞお健やかにお過ごしください。
本年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和〇年 一月
4.2.2 喪中の方へご挨拶する場合の文例
寒中お見舞い申し上げます。
ご服喪中と存じ、年始のご挨拶は遠慮させていただきました。
その後、お変わりなくお過ごしでしょうか。
まだまだ寒さ厳しい折、どうかご無理なさらないでくださいね。〇〇様とご家族の皆様が、穏やかな日々を過ごされますよう心よりお祈りしております。
令和〇年 一月
喪中の方へ送る際は、お祝いの言葉や、近況報告で華やかな話題は避けるのが心遣いです。「年賀状」という言葉も使わず、「年始のご挨拶」「新年のご挨拶」などと表現を和らげると良いでしょう。より詳しいマナーについては、日本郵便のウェブサイトも参考になりますよ。
4.2.3 一般的な季節の挨拶として送る場合の文例
寒中お見舞い申し上げます。
例年にない寒さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
おかげさまで、私どもは元気に暮らしております。
春の訪れが待ち遠しい今日この頃、くれぐれもご自愛くださいませ。
令和〇年 一月
5. スピーチや朝礼で使える1月の挨拶
新しい年の始まりには、職場での朝礼や地域の集まりなどで、挨拶を頼まれる機会があるかもしれませんね。大勢の前で話すのは少し緊張するものですが、せっかくなら聞いている人の心に届くような、温かい言葉を届けたいものです。
1月のスピーチでは、長々と話すよりも、新しい年への期待感や、周りの人への感謝の気持ちを簡潔に伝えるのが素敵です。少しだけ個人的な抱負や目標を交えると、あなたらしさが伝わり、聞いている人も親しみを感じてくれるはずですよ。
5.1 新年の抱負を交えた挨拶の例文
新しい年の始まりに、前向きな気持ちや目標を共有することで、場が明るく活気づきます。ご自身の言葉で、今年楽しみにしていることなどを話してみましょう。
【職場での朝礼を想定した例文】
「皆さん、あけましておめでとうございます。
清々しい新年の幕開けを、皆さんと共に迎えることができ、大変嬉しく思います。旧年中は、公私にわたり大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
さて、私個人のささやかな目標ですが、今年はもう少し時間にゆとりを持って、一日ひとつ、新しい発見をすることを心がけたいと思っています。仕事の進め方を見直したり、帰り道にいつもと違う道を通ってみたり。そんな小さな変化を楽しみながら、心豊かに過ごしたいです。
まだまだ未熟な私ですが、皆さんと力を合わせ、この一年を実り多いものにしていきたいと願っております。本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんのこの一年が、素晴らしいものになりますよう心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。」
5.2 健康を気遣う言葉を入れた挨拶の例文
一年で最も寒さが厳しい1月。相手の健康を思いやる一言は、聞く人の心を温めてくれます。特に、ご自身の経験を交えながら話すと、より気持ちが伝わりますよ。
【地域の集まりなどを想定した例文】
「新年おめでとうございます。皆様、お健やかに新しい年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
お正月の賑わいも落ち着き、これからが寒さの本番ですね。私も、最近は朝起きるときのひんやりとした空気で、きゅっと身が引き締まる思いです。
どうぞ皆様、暖かくしてお過ごしくださいね。美味しいものを食べて、たくさん笑って、心も体も健やかに、笑顔の多い一年にしてまいりましょう。
本年も皆様とご一緒に行事などを楽しめますことを、心待ちにしております。どうぞよろしくお願いいたします。皆様のこの一年が、幸多きものとなりますよう、心よりお祈りしております。」
6. 1月の挨拶を書く際に知っておきたい注意点
新しい年のはじまりである1月は、おめでたい雰囲気に包まれていますね。だからこそ、相手に失礼のないよう、挨拶には少しだけ心を配りたいもの。知らず知らずのうちに相手を不快にさせてしまわないよう、基本的なマナーをいくつかご紹介します。ほんの少し意識するだけで、あなたの細やかな心遣いがきっと伝わりますよ。
6.1 松の内を過ぎた場合の挨拶マナー
お正月の挨拶でよく耳にする「松の内」という言葉。これは、お正月に飾る門松を飾っておく期間のことを指します。この期間を過ぎたら、新年の挨拶の仕方も少し変わってきます。
松の内の期間は地域によって違いがあり、関東では1月7日まで、関西では1月15日までとするのが一般的です。もし相手の住む地域がわからない場合は、1月7日までを目安にすると丁寧でしょう。
そして大切なのが、この松の内を過ぎた場合、「あけましておめでとうございます」というお祝いの言葉(賀詞)は使わないのがマナーとされています。その代わりとして、次のような言葉を使うと良いでしょう。
- 「本年もどうぞよろしくお願い申し上げます」
- 「寒中お見舞い申し上げます」
「あけましておめでとうございます」は松の内まで、と覚えておくと、いざという時にスマートな挨拶ができますね。
6.2 忌み言葉を避ける配慮
おめでたい新年の挨拶では、縁起が悪いとされる「忌み言葉」を避けるのが昔からの習わしです。これは、相手の新しい一年が素晴らしいものになるように、という願いを込めた日本らしい思いやりのかたち。特に手紙やメールなど、文章として残るものには気をつけたいところです。
うっかり使ってしまいがちな言葉もありますので、下の表で確認してみましょう。より丁寧で素敵な表現に言い換えることができますよ。
| 避けたい忌み言葉 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 去年 | 昨年、旧年(「去る」という言葉を避けるため) |
| 失う、倒れる、破れる、枯れる、衰える、終わる | おめでたい場にふさわしくないため、使わないようにしましょう。 |
| 病む、苦しむ | 相手の健康を気遣う文脈でも、直接的な表現は避けるのが無難です。「ご無理なさらないでくださいね」などの表現に。 |
また、文章の「区切り」や「終わり」を連想させるため、句読点(「、」や「。」)を使わないのが正式なマナーとされています。とはいえ、現代では読みやすさを優先して句読点を使うことも多くなっています。親しい間柄であれば、あまり気にしすぎる必要はないかもしれませんね。
こうしたマナーについて、日本郵便のウェブサイトでも詳しい解説がありますので、参考にしてみるのもおすすめです。
年賀状のタブー(使ってはいけない言葉)は? – 日本郵便
一番大切なのは、相手を思う気持ちです。これらの心遣いを少し添えるだけで、あなたの挨拶がより温かく、心に残るものになるはずですよ。
7. まとめ
新しい年の始まり、清々しい気持ちで挨拶を交わしたいものですね。1月の挨拶は、松の内が明ける前後や大寒の頃など、時期によって使う言葉が変わるのが特徴です。ビジネスメールから親しい方へのLINEまで、相手や場面に合わせた言葉選びが、丁寧な心遣いとして伝わることでしょう。この記事でご紹介した文例が、あなたの言葉にそっと寄り添い、温かな人間関係を育む一助となれば幸いです。










コメント