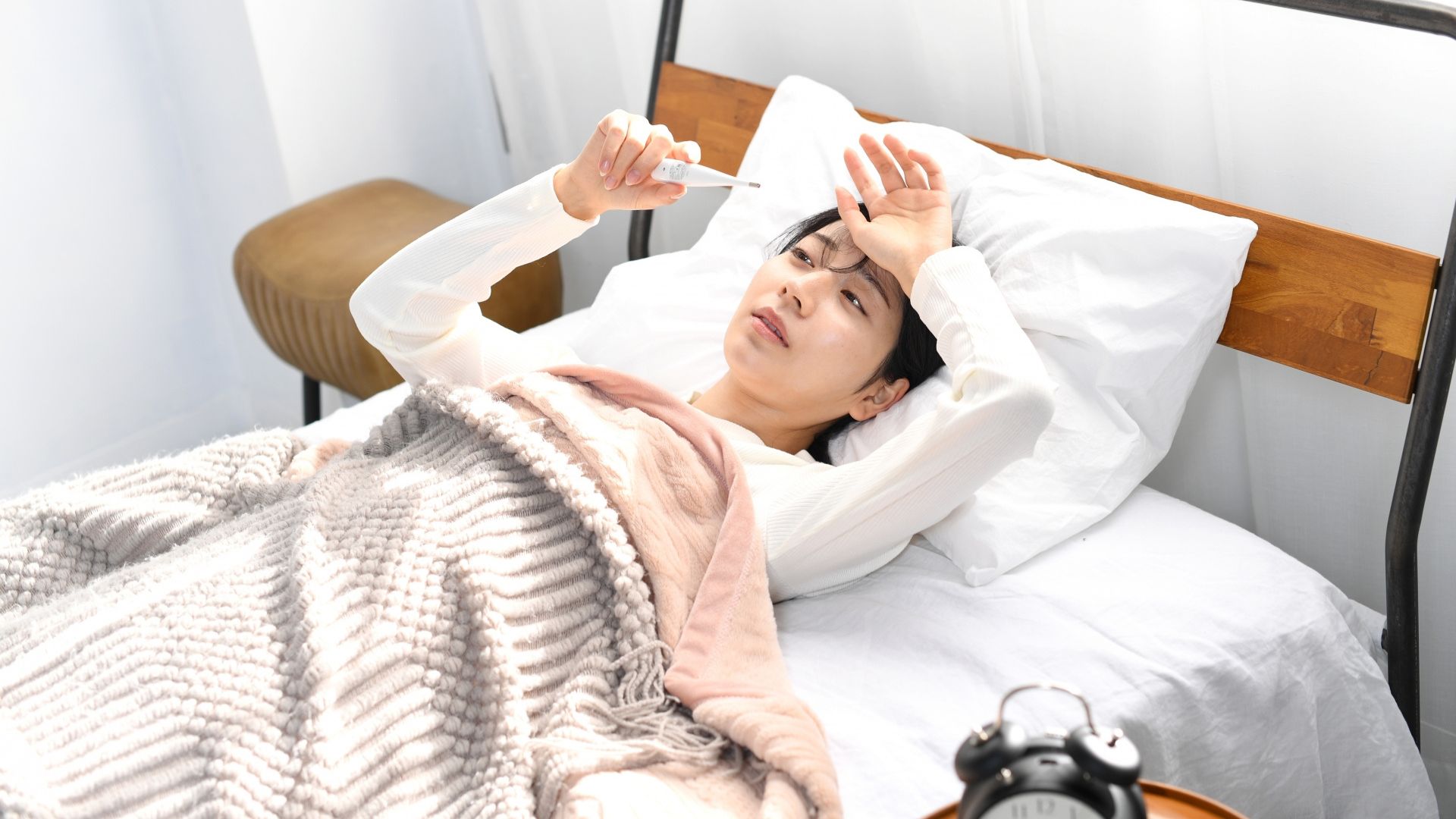脇で体温を測ると、右と左で数値が違って「どちらが正しいの?」と戸惑うことはありませんか。実は、利き手による筋肉量の違いや血流、あるいは体温計の当て方ひとつで、体温に左右差が生じるのは珍しくないのです。この記事を読めば、その理由や正しい体温測定方法、そして注意すべき体温差の目安までスッキリ分かります。日々の健康管理にお役立てくださいね。
1. 脇の体温に左右差が出るのはなぜ
「あれ?右と左で体温が違う…」なんて、脇で体温を測ったときに不思議に思ったことはありませんか。実は、私たちの体温は、測る場所や体の状態によって少しずつ変わるものなんです。特に脇の下で測る体温は、ちょっとしたことで左右差が出やすいと言われています。でも、ご安心ください。多くの場合、この左右差は体の自然な反応や、測り方の影響によるものなんですよ。ここでは、どうして脇の体温に左右差が生まれるのか、その気になる理由を一緒に見ていきましょう。

1.1 利き手や血流が体温の左右差に関係するの
私たちの体は、完璧な左右対称というわけではありません。日々の生活の中での体の使い方や、もともとの体のつくりによって、微妙な違いがあるんですよ。それが体温の左右差にもつながることがあります。
例えば、利き手側は無意識のうちによく動かすため、筋肉が発達しやすく、それに伴って血流も多くなる傾向があります。筋肉は熱を生み出す場所ですから、活動的な利き手側のほうが少し体温が高く出ることがあるんですね。また、心臓は体の中心よりもやや左側に位置しています。そのため、心臓から送り出される血液の流れが、左右でわずかに異なることも、体温の左右差に影響を与えると考えられています。太い血管の通り道も、左右で完全に同じではないため、そういった体の内部構造の違いも、繊細な体温に反映されることがあるのです。
このように、利き手による活動量の違いや、体の中心を流れる血液の循環具合などが、脇の下の体温に微妙な差を生む一因となっているのですね。
1.2 測り方や環境も体温の左右差に影響
体温の左右差は、体の内部的な要因だけでなく、体温を測るときの方法や周りの環境によっても大きく変わることがあります。正しい測り方を知っておくことは、より正確な体温を知る上でとても大切です。
例えば、体温計を脇に挟む角度が浅かったり、脇がしっかり閉じていなかったりすると、外気の影響を受けてしまい、本来の体温よりも低く測定されてしまうことがあります。左右どちらか一方で測り方が適切でなかった場合、それがそのまま左右差として現れるわけです。また、脇に汗をかいていると、汗が蒸発するときに皮膚の熱を奪うため(気化熱といいます)、体温が低めに出てしまうことも。左右で汗のかき具合が異なれば、それが左右差の原因になることも考えられますね。
その他にも、以下のような要因が体温の左右差に影響を与えることがあります。
| 影響を与える要因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 衣服の状態 | 片側だけ厚着をしていたり、カイロなどを当てていたりすると、その部分の皮膚温が上がり、体温が高く測定されることがあります。 |
| 室温 | 寒い部屋で体温を測ると、体の表面温度が下がりやすいため、正確な測定が難しくなることがあります。特に体の冷えやすい側は、より低く測定される可能性があります。 |
| 測定前の行動 | 測定直前に片側だけを下にしていたり、圧迫していたりすると、その部分の血流が一時的に変化し、体温に影響が出ることがあります。 |
このように、体温計の当て方ひとつ、あるいはその時のちょっとした環境の違いが、体温の左右差につながることがお分かりいただけたでしょうか。より詳しい体温の測り方については、次の章でご紹介しますね。
体温の左右差について、テルモ株式会社のウェブサイトでも情報が提供されています。ご興味のある方は、こちらも参考にしてみてください。
テルモ株式会社 体温計に関するよくあるご質問 Q.左右の脇の下で測った体温が違うのですが?
2. 正しい体温測定方法を知って体温の左右差を理解しよう
体温の左右差が気になる時、もしかしたら体温の測り方が影響しているのかもしれません。正しい測り方を知ることは、体温の左右差を正しく理解するための第一歩です。ここでは、体温計の種類や選び方、そして脇で正しく体温を測るための手順を丁寧にご紹介しますね。
2.1 体温計の種類と選び方
ひとくちに体温計といっても、実はいろいろな種類があるんですよ。ご家庭でよく使われるのは「電子体温計」ですが、その中でも測定方式によって特徴が異なります。それぞれの特徴を知って、ご自身に合ったものを選びましょう。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 実測式電子体温計 | 舌下や脇の下などで、実際の温度をそのまま測るタイプです。平衡温(それ以上上がらない温度)を測ります。 | 精度が高いのが特徴です。 | 測定に時間がかかります(脇で約10分、舌下で約5分)。 |
| 予測式電子体温計 | 測定開始からの温度上昇を分析し、平衡温を予測して表示するタイプです。多くの製品は予測測定後、そのまま実測測定も続けられます。 | 短時間(数十秒~1分程度)で測定できるので手軽です。 | 測り方や体温計を当てる場所が正しくないと、誤差が出やすいことがあります。 |
| 非接触型体温計(赤外線体温計) | 額などから放射される赤外線量を測定して体温を推定します。肌に触れずに測れるのが特徴です。 | 衛生的で、寝ている人や小さなお子さんにも使いやすいです。 | 外気温や汗、化粧などの影響を受けやすく、脇で測る体温計に比べて精度がやや劣る場合があります。 |
脇で体温を測る場合、より正確な体温を知りたい場合は実測式、手軽に測りたい場合は予測式がおすすめです。予測式でも、メーカーの指示通りに正しく使えば、日常の健康管理には十分役立ちますよ。ご自身の使い方や求める精度に合わせて選んでみてくださいね。
体温計の選び方や使い方について、さらに詳しい情報は、一般社団法人 日本医療機器産業連合会の「体温計Q&A」も参考になりますので、ご覧になってみてください。
2.2 脇で正しく体温を測る手順
脇で体温を測るとき、ちょっとしたコツで測定結果が変わることがあります。いつも同じように、そして正確に測るための手順を一緒に確認していきましょう。
2.2.1 測定前の準備
体温を測る前には、いくつか準備しておきたいことがあります。これらの準備をすることで、より正確な体温を知ることができますよ。
- 安静にする:運動した後や入浴後、食事の後は体温が上がりやすいので、30分以上経ってから測りましょう。また、部屋に入ってすぐなど、体が室温に慣れていない時も避け、しばらく落ち着いてから測定するのがおすすめです。
- 脇の汗を拭く:脇に汗をかいていると、体温が低く測定されてしまうことがあります。乾いたタオルなどで優しく拭き取ってから測りましょう。
- 体温計の準備:体温計の電源を入れ、表示を確認します。前回測定した値が表示される機種もあるので、リセットされているか確認しましょう。
2.2.2 体温計の正しい当て方と測定時間
体温計を脇に当てる角度や位置も、正確な測定にはとても大切です。以下のポイントを押さえて、丁寧に測ってみましょう。
- 体温計の先端を脇の中心に当てる:脇のくぼみの一番深いところに、体温計の先端(感温部)をしっかりと当てます。
- 体温計の角度:体温計を脇に対して、下から少し押し上げるようなイメージで、体に対して30~45度くらいの角度で挟み込みます。体温計が浮かないように、しっかりと密着させることがポイントです。
- 脇をしっかり閉じる:体温計を挟んだら、脇をしっかりと閉じます。反対側の手で、体温計を挟んでいる方の腕を軽く押さえると、より密着しやすくなりますよ。特に冬場など、衣服が厚い場合は、体温計が直接肌に触れるように注意しましょう。
測定時間は、お使いの体温計の種類によって異なります。実測式の場合は一般的に10分程度、予測式の場合は電子音が鳴るまで(数十秒から1分程度)が目安です。予測式体温計の多くは、予測検温が終わった後もそのまま実測検温を続けられるようになっています。より正確な体温を知りたい場合は、予測検温のアラームが鳴った後も、そのまま実測検温の時間(取扱説明書に記載されています)まで測り続けるのがおすすめです。必ずお使いの体温計の取扱説明書を確認し、正しい測定時間を守るようにしてくださいね。
3. 体温の左右差が大きいときに考えられる原因
脇で測る体温に左右で差があると、「もしかして何かの病気かしら?」と不安に感じてしまうかもしれませんね。でも、ご安心ください。体温の左右差には、心配のいらない一時的なものから、少し注意が必要なケースまで、いくつかの理由が考えられるのです。ここでは、その原因について、一緒に見ていきましょう。
3.1 一時的な体温の左右差とその要因
多くの場合、体温の左右差は私たちの日常生活の中のささいなことや、体の自然な反応によって生じます。このような一時的な左右差であれば、過度に心配しすぎることはありませんよ。どのような要因があるのか、具体的に見てみましょう。
主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 利き手や活動量の影響:利き手側は無意識のうちによく動かしているため筋肉が発達しやすく、血行も活発になりがちです。そのため、反対側よりも少し体温が高くなることがあります。これは自然な体の仕組みなのですね。
- 衣服や寝具の影響:片側だけ厚着をしていたり、寝ている間に無意識に片側だけお布団がめくれていたりすると、その部分の皮膚温が変わり、体温に差が出ることがあります。
- 測定時の環境:例えば、ストーブなど暖房器具のすぐそばで測った側や、逆に冷たい壁に体が触れていた側など、周囲の温度環境によっても影響を受けることがあります。
- 測定方法のちょっとした違い:脇の汗をしっかり拭き取らずに測定したり、体温計を挟む角度が浅かったり、脇の締め方がゆるかったりすると、正確な体温が測れず、左右で数値が異なってしまうことがあります。
- 入浴や運動の直後:お風呂上がりや運動の後は、体全体の体温が一時的に上がっています。その際、体の冷え方や温まり方に左右でわずかな差が生じ、体温差として現れることがあります。
- 食事や飲酒の後:食事をすると消化のために内臓の血流が活発になったり、アルコールを飲むと血管が拡張したりします。こうした血流の変化が一時的に体温の左右差として現れることもあります。
これらの要因による左右差は、多くの場合0.5℃程度までで、一過性のものです。時間をおいて測り直したり、衣服や室温などの環境を整えたりすることで解消されることがほとんどですので、あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。もし気になるようでしたら、一度深呼吸して、条件を変えて測り直してみてくださいね。
3.2 注意したい体温の左右差 病気の可能性も
一方で、体温の左右差がいつも1℃以上の大きな差が続く場合や、左右差とともに他に何か気になる症状がある場合は、もしかすると何らかの病気が背景にある可能性も考えられます。そのような場合は、ご自身だけで判断せず、一度医療機関を受診することをおすすめします。
体温の左右差が見られる可能性のある病気には、以下のようなものがあります。少し専門的なお話も含まれますが、知っておくと安心につながるかもしれません。
| 考えられる病気 | 主な症状や左右差との関連 |
|---|---|
| 血管系の病気(例:閉塞性動脈硬化症、大動脈炎症候群など) | 手足の冷えやしびれ、痛み、脈拍の左右差などがみられることがあります。血管が狭くなったり詰まったりして血流が悪くなっている側の体温が、もう片方より低くなる傾向があります。 |
| リンパ系の病気(例:リンパ浮腫、リンパ節炎など) | 片側の腕や足がむくむ、重だるい感じがする、皮膚が硬くなるなどの症状が現れることがあります。リンパの流れが悪くなることで、炎症や血行不良が起こり、体温にも影響が出ることがあります。 |
| 局所的な炎症や感染症(例:乳腺炎、蜂窩織炎、関節炎など) | 体の特定の部分に炎症や感染が起こると、その部分が赤く腫れたり、熱を持ったり、痛んだりします。炎症が起きている側の体温が、その部分を中心に高くなることがあります。 |
| 自律神経の乱れ | ストレスや不規則な生活、更年期などによって自律神経のバランスが崩れると、体温調節機能がうまく働かなくなることがあります。その結果、冷えやのぼせ、異常な発汗などとともに、体温の左右差として現れることも考えられます。 |
| 甲状腺機能の異常(例:甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症など) | 甲状腺ホルモンのバランスが崩れると、全身の代謝に影響が出ます。動悸、体重の増減、倦怠感、暑がり・寒がりなどの症状が主ですが、稀に体温調節のアンバランスから左右差を感じる方もいるかもしれません。 |
これらの病気は、早期に気づき、適切な対応をすることがとても大切です。体温の左右差だけでなく、他に何か「いつもと違うな」と感じる症状(例えば、片側の手足の冷えやむくみが続く、原因不明の痛みやしびれがある、皮膚の色がおかしい、リンパ節が腫れている、微熱が続くなど)がある場合は、どうぞお一人で悩まず、かかりつけのお医者様や専門の医療機関にご相談くださいね。医師は、お話を聞き、必要な診察や検査を通じて、的確な判断をしてくださいます。
特に、急に大きな体温差が現れたり、強い痛みを伴ったりする場合は、ためらわずに速やかに医療機関を受診するようにしましょう。ご自身の体の声に耳を傾け、健やかな毎日を送るための一歩としてくださいね。
4. 子供の体温測定と左右差のポイント
小さなお子さまの体温測定は、なかなかじっとしていてくれなかったり、嫌がってしまったりと、お母さま方もご苦労が多いことでしょう。ここでは、赤ちゃんや子供の体温測定の際の注意点や、体温の左右差について知っておきたいポイントを、わかりやすくお伝えしますね。
4.1 赤ちゃんや子供の体温測定の注意点
赤ちゃんや小さなお子さまは、大人に比べて体温調節機能がまだ未熟です。そのため、室温や衣類、ちょっとした活動によっても体温が変動しやすいという特徴があります。まずは、落ち着いて正確に測るための基本的な注意点をおさえておきましょう。
体温測定をスムーズに行うためには、いくつかのポイントがあります。以下の表にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
| ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 測定のタイミング | 食事の直後、運動や入浴の直後、泣いた後などは体温が上がりやすいため避け、できるだけ安静な状態で機嫌の良い時に測りましょう。朝起きた時や午前中、夕方など、時間を決めて測ると平熱の把握にも役立ちます。 |
| 測定前の準備 | 脇の下で測る場合は、汗をかいていたら乾いたタオルで優しく拭き取ってから測りましょう。厚着をしていると熱がこもりやすいので、衣類を調整することも大切です。部屋の温度も、暑すぎたり寒すぎたりしないように気を配りましょう。 |
| 体温計の選び方と使い方 | 脇で測る電子体温計のほか、耳で測る耳式体温計、おでこで測る非接触型体温計などがあります。それぞれ特徴が異なりますので、お子さまの年齢や状況に合わせて使いやすいものを選びましょう。脇で測る場合は、体温計の先端を脇のくぼみの中央にしっかり当て、腕を体に密着させることが大切です。 |
| 嫌がるお子さまへの対応 | 体温測定を嫌がるお子さまには、無理強いせず、遊びの延長のように声かけをしたり、安心できるような言葉をかけたりすると良いでしょう。「もしもしするね」「ピッてするよ」など、優しく話しかけながら行うと、お子さまも落ち着きやすいかもしれません。 |
| 普段の平熱を知る | 健康な時の平熱を把握しておくことが、いざという時の判断基準になります。毎日同じ時間帯に体温を測り、記録しておくと良いでしょう。体温だけでなく、機嫌や食欲、顔色なども一緒に観察しておくと、体調の変化に気づきやすくなります。 |
特に赤ちゃんの場合、言葉で不調を訴えることができません。日頃から体温を測る習慣をつけ、ちょっとした変化にも気づけるようにしておくと安心ですね。
4.2 子供の体温の左右差で気をつけること
大人と同じように、子供の体温にも左右差が見られることがあります。多くの場合、利き手側や、寝ていた時に下になっていた側が高くなるなど、生理的な要因によるものです。また、測り方によっても差が出ることがありますので、まずは正しく測れているかを確認しましょう。
一般的に、0.5℃程度のわずかな左右差であれば、それほど心配する必要はないと言われています。しかし、次のような場合は注意が必要です。
- 1℃以上の大きな左右差が続く場合
- 片方の脇だけが明らかに熱く感じる、赤みがある、腫れているなどの局所的な症状が見られる場合
- 発熱以外に、機嫌が悪い、ぐったりしている、食欲がない、嘔吐や下痢など、他の気になる症状がある場合
このような場合は、中耳炎やリンパ節の炎症など、体の片側に何らかの炎症が起きている可能性も考えられます。特に、耳の下や首、脇の下にしこりや腫れがあり、触ると痛がるような場合は、リンパ節炎の可能性も考慮し、早めにかかりつけの小児科医に相談することをおすすめします。
体温の左右差だけで病気と判断することはできませんが、普段と違う様子が見られたり、気になる症状が伴ったりする場合は、自己判断せずに専門医の診察を受けるようにしましょう。その際、いつから左右差があるのか、他にどんな症状があるのかなどを伝えられるように、メモしておくと診察がスムーズに進みますよ。
5. 体温の左右差に関するよくある質問
脇で測る体温の左右差について、皆さまからよく寄せられるご質問にお答えします。日々の健康管理にお役立ていただけると嬉しいです。
5.1 体温は左右どちらで測るのがおすすめ
体温を測る際、左右どちらの脇で測るべきか迷うことがありますね。基本的には、どちらの脇で測っても問題ありませんのよ。ただし、いくつかのポイントがございます。
一般的に、利き手ではない方の脇で測る方が、体温計をしっかりと挟みやすく、安定した測定ができると言われています。利き手側は日常的によく動かすため、筋肉量が多く血流も活発になりがちで、もう片方よりもわずかに体温が高く出ることがあります。でも、これは個人差が大きい部分です。
ご自身の平熱をより正確に知るためには、何度か左右両方の脇で測ってみて、どちらが測りやすいか、あるいはどちらの値を採用するかをご自身で決めるのがよろしいでしょう。もし、より厳密な平均値を知りたい場合は、両方で測ってその平均をとるという方法もございます。
大切なのは、毎回同じ条件で測ること。もし「こちら側で測る」と決めたら、できるだけ同じ脇で測り続けることをおすすめします。そうすることで、日々の体温変化をより正確に捉えることができます。
5.2 体温の左右差は何度までが許容範囲
脇で測った体温に左右差があるのは、ある程度は自然なことなのですよ。健康な方であれば、一般的に0.2℃から0.5℃程度の差は許容範囲内と考えられています。これは、体の中心からの距離や、周囲の血管の太さ、脂肪のつき方などが左右で微妙に異なるために生じるものです。
ただし、この数値はあくまで目安です。測定時の体温計の挟み方や、直前の活動量、室温などによっても左右差は変動することがありますから、少し差があったからといって、すぐに心配する必要はありませんわ。
注意が必要なのは、普段と比べて急に左右差が大きくなった場合や、常に1℃以上の差が見られるような場合です。特に、片側の脇の下のリンパ節が腫れていたり、炎症があったりすると、その側の体温が局所的に高くなることがあります。もし、体温の左右差とともに、だるさや痛み、腫れなどの他の症状がある場合は、念のため医療機関にご相談なさるのが安心ですね。
体温の左右差について、一般的な目安をまとめてみましたので、参考にしてくださいませ。
| 左右差の程度 | 考えられること | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 0.5℃程度まで | 生理的な範囲内、または測定条件による差 | 特に心配いりませんが、毎回同じ条件で測るよう心がけましょう。 |
| 0.5℃~1.0℃未満 | 個人差の範囲内の可能性が高いですが、継続する場合は注意 | 他の症状がなければ様子を見ても良いですが、差が大きくなる場合は注意が必要です。 |
| 1.0℃以上 | 局所的な炎症や血流障害、または何らかの疾患の可能性 | 他の症状がなくても、一度医療機関に相談することをおすすめします。 |
この表はあくまで一般的な目安ですので、ご自身の体調と合わせて総合的に判断なさってくださいね。
5.3 毎回同じ側で体温を測る必要はあるの
日々の健康管理や、風邪などで熱が出たときの経過観察のためには、できる限り毎回同じ側の脇で体温を測ることを強くおすすめします。
先ほどお話ししましたように、体温は左右の脇で微妙に異なることがあります。そのため、測る側を変えてしまうと、その日の体温が本当に変化したのか、それとも測る側を変えたことによる測定値の違いなのか、判断がつきにくくなってしまうのです。
特に、基礎体温を記録されている方や、お子さまの発熱の様子を細かく見守りたい時などは、測定条件を一定に保つことが非常に大切です。いつも同じ時間に、同じ体温計で、そして同じ側の脇で測ることで、わずかな体温の変化にも気づきやすくなります。
「どちらで測ったか忘れてしまいそう…」という方は、体温手帳などに記録する際に、測った側(右か左か)も一緒にメモしておくと良いでしょう。あるいは、「私はいつも左側で測る」というように、ご自身の中でルールを決めてしまうのも、忘れにくくておすすめです。
このように、一貫性のある測定を心がけることで、ご自身の体調の変化をより正確に把握し、健やかな毎日を送るための一助となります。もし、体温測定についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、体温計メーカーのウェブサイトなども参考になります。
6. まとめ
脇で測る体温に左右差が生じるのは、利き手による筋肉量の違いや血流、さらには測定時の室温や体温計の当て方といった、さまざまな要因が複合的に影響しているためです。まずは正しい体温測定方法を身につけ、ご自身の平熱を把握することが大切ですね。普段と比べて体温の左右差が著しく大きい場合や、体調に変化を感じる際には、何らかの不調のサインかもしれませんので、医療機関にご相談いただくことをおすすめします。この記事が、日々の健康管理を見直すきっかけとなれば幸いです。