一年の労をねぎらい、新たな気持ちで新年を迎えるための大切な節目、忘年会。その本来の意味や由来を紐解きながら、今年初めて幹事を任されたあなたの不安にそっと寄り添い、準備から当日までを丁寧にサポートする情報をお届けします。この記事では、忘年会という行事の基本知識はもちろん、企画の立て方からお店選びのコツ、参加者が心から楽しめる出し物やゲーム、そして様々な場面でそのまま使える挨拶の例文まで、幹事として知っておきたいことのすべてを詰め込みました。参加者全員の記憶に残る素敵な忘年会を成功させる秘訣は、事前の丁寧な準備と、参加者一人ひとりへの細やかな心配りにあります。この記事が、あなたにとって最高の忘年会を創り上げるための一助となれば幸いです。
1. 忘年会とは何か 基本知識を解説
年の瀬も押し迫ると、街はきらびやかなイルミネーションで彩られ、なんだか心がそわそわしてきますね。この時期になるとよく耳にするのが「忘年会」という言葉。職場の仲間や親しい友人たちと集まる楽しい宴会ですが、そもそもどのような意味があるのか、ご存知でしょうか。ここでは、忘年会が持つ本来の意味や歴史、いつ頃行うのが良いのかなど、知っているとちょっと自慢できる基本の知識を丁寧にご紹介します。

1.1 忘年会が持つ本来の意味
「忘年会」という言葉の通り、その一番の意味は「年を忘れるための会」です。これは、その年一年にあった仕事の苦労や嫌な出来事をすべて忘れて、新しい気持ちで新年を迎えよう、という願いが込められています。単にお酒を飲んで騒ぐだけの会ではないのですね。
また、忘年会は一年間お世話になった方々へ感謝を伝え、お互いの頑張りをねぎらう「慰労会(いろうかい)」としての側面も持っています。上司や部下、同僚といった垣根を越えて、今年一年の頑張りをたたえ合う、とても温かい意味合いがあるのです。昔から言われる「無礼講(ぶれいこう)」も、この時ばかりは立場を気にせず楽しもうという気持ちの表れですが、もちろん最低限の礼儀は大切にしたいものですね。
1.2 忘年会の起源と歴史的な由来
忘年会のルーツをたどると、なんと鎌倉時代にまでさかのぼると言われています。当時は「年忘れ(としわすれ)」と呼ばれ、貴族や武士たちが年末に集まり、連歌(れんが)を詠みながら静かに一年を振り返る、とても風流な会だったそうです。今のような賑やかな宴会とは、少し趣が違っていたのですね。
現在のような宴会の形に近づいたのは、江戸時代のこと。武士だけでなく庶民の間にも「年忘れ」の習慣が広まり、お酒を酌み交わしながら楽しむスタイルが定着していきました。そして明治時代に入り、「忘年会」という言葉が一般的に使われるようになり、会社や組織の公式行事として年末に行われる文化が根付いていったのです。時代とともに形は変わっても、一年の苦労をねぎらい、新たな年へ向かうという心は、昔からずっと受け継がれているのですね。
1.3 忘年会を行うのに最適な時期
忘年会は、その名の通り「年を忘れる」会なので、一般的には年末である12月に行われます。特に、多くの会社で仕事納めが近くなる12月の第2週から第3週の金曜日は、忘年会のピークと言われ、お店の予約も集中します。
ただ、最近では参加者の都合やお店の混雑を避けるため、少し時期をずらすケースも増えてきました。それぞれの時期にメリットがありますので、幹事になった際の参考にしてみてくださいね。
| 開催時期 | 特徴やメリット |
|---|---|
| 11月下旬~12月上旬 | お店の予約が比較的取りやすく、料金も手頃な場合があります。参加者の年末の忙しさを避けられるのも嬉しいポイントです。 |
| 12月中旬(特に金曜日) | 最も「忘年会らしい」雰囲気で盛り上がれる時期です。ただし、予約競争が激しく、早めの計画が欠かせません。 |
| 12月下旬(仕事納め前後) | 「今年も一年お疲れ様でした!」という締めくくりの気持ちを、参加者全員で共有しやすいタイミングです。 |
| 1月(新年会と兼ねて) | 年末の慌ただしさを避け、落ち着いて開催できます。「新年会」として、新たな年の始まりを祝う会にするのも素敵ですね。 |
このように、必ずしも12月に行わなければならない、という決まりはありません。参加する方々が心から楽しめる日を選ぶことが、何よりも大切なのかもしれませんね。
2. 忘年会の幹事がやるべきこと完全リスト
忘年会の幹事を任されると、「何から手をつければいいのかしら?」と少し戸惑ってしまいますよね。でも、ご安心ください。忘年会の成功は準備で8割決まると言われるほど、事前の段取りが大切なのです。ここでは、やるべきことを順番に沿ってご紹介しますので、一つひとつ確認しながら進めていきましょう。このリストがあれば、初めての幹事でもきっと大丈夫ですよ。
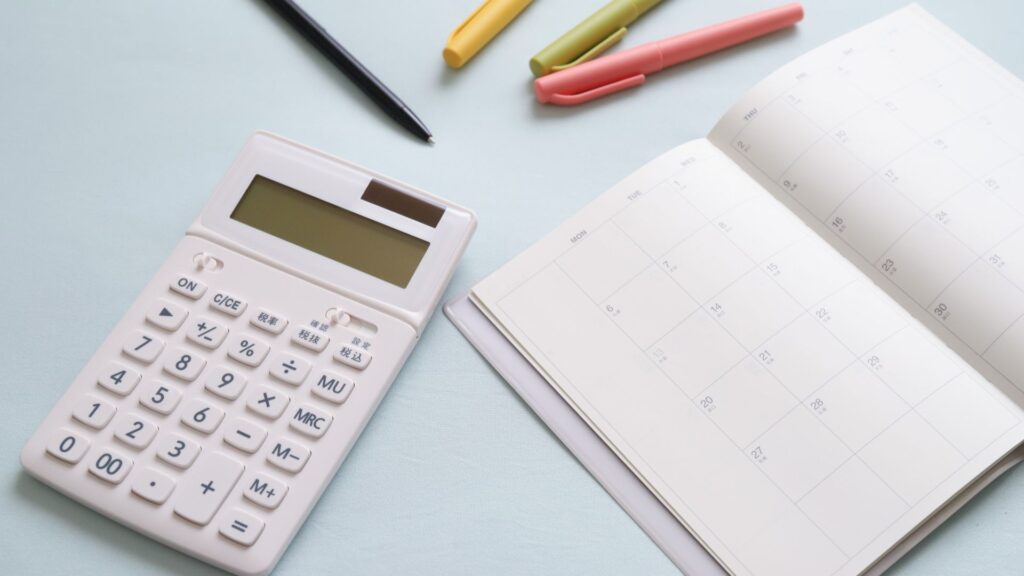
2.1 企画立案から会場予約までの流れ
まずは、忘年会の骨格となる企画を立て、お店を予約するところから始めます。ここが一番の頑張りどころ。参加する皆さんの笑顔を思い浮かべながら、楽しい計画を立てていきましょう。
大まかな流れは次の通りです。忘年会の日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むのがおすすめです。
| 時期の目安 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1ヶ月~3週間前 | 日程調整・お店の候補選び | 複数の候補日とお店をリストアップしておくとスムーズです。 |
| 3週間前 | お店の予約 | 人数の変更が可能か、キャンセル料はいつから発生するかを確認しましょう。 |
| 2~3週間前 | 参加者への案内 | 日時、場所、会費などを明記した案内メールを送ります。 |
| 1~2週間前 | 出欠の確認・人数の確定 | お店に最終的な参加人数を連絡します。 |
| 1週間前~前日 | 当日の準備(挨拶の依頼、景品購入など) | 当日の進行表(タイムテーブル)を作成し、関係者で共有しておくと安心です。 |
2.1.1 日程調整とお店選びのコツ
忘年会準備の第一歩は、参加者の都合が良い日を探すことから始まります。12月は誰もが忙しい時期ですから、早めに動き出すことが肝心です。
日程調整では、候補日を3つほど挙げて、参加者に都合を尋ねるのが良いでしょう。「調整さん」や「LINEスケジュール」といった無料のツールを使うと、みんなの回答が一覧でわかり、とても便利ですよ。一般的に、週末の金曜日や土曜日は人気が集中し、予約が取りにくい傾向にあります。もし可能であれば、週の半ばを候補に入れると、お店の選択肢も広がるかもしれません。
お店選びは、忘年会の満足度を左右する大切なポイントです。参加者全員が心地よく過ごせるようなお店選びを心がけましょう。会社の近くや主要駅の周辺など、集まりやすくて帰りやすい場所が喜ばれます。また、参加者の年齢層を考えて、落ち着いた雰囲気の和食店や、少しおしゃれなイタリアンなど、好みに合いそうなお店を探してみてください。予算管理がしやすい「飲み放題付きのコース」があるお店を選ぶと、当日の会計もスムーズです。個室があるか、アレルギーを持つ方への対応は可能かといった点も、予約の際に確認しておくと、より丁寧な印象になります。
2.1.2 予算の決め方と会費の相場
次に、お金の話です。忘年会の予算と会費を決めましょう。まず確認したいのが、会社からの補助金が出るかどうかです。総務部や上司に尋ねてみてくださいね。
一般的な会社の忘年会では、一人当たりの会費は4,000円から6,000円程度が相場とされています。この金額を基準に、お店のコース料金や、後ほどご紹介するゲームの景品代などを考えて予算を組み立てます。もし、景品を少し豪華にしたい場合は、その分を会費に上乗せすることも考えましょう。
会費を集める際には、役職によって金額に差をつける「傾斜配分」という方法もあります。例えば、部長は8,000円、課長は7,000円、一般社員は5,000円というように、役職が上の方に少し多めに負担していただく考え方です。これは会社の慣習にもよりますので、過去の幹事経験者や上司に相談してみると良いでしょう。
2.2 案内メールの書き方と出欠管理
日程と場所、会費が決まったら、いよいよ参加者の皆さんへ案内メールを送ります。メールは、誰が読んでも分かりやすいように、必要な情報を簡潔にまとめるのがコツです。
件名は「【〇月〇日開催】忘年会のご案内(〇〇部)」のように、一目で内容がわかるものにしましょう。本文には、以下の項目を箇条書きで記載すると、情報が伝わりやすくなります。
- 開催日時
- お店の名前と住所(お店のホームページや地図のURLを添えると親切です)
- 会費
- 出欠の返信締切日
- 幹事の連絡先
そして、忘れてはならないのが出欠の管理です。出欠の返信締切日は必ず設けましょう。締切日を設定することで、お店への最終的な人数報告がスムーズに行えます。誰が出席で誰が欠席なのかを一覧表にしておくと、管理がしやすくなりますよ。簡単な手書きのメモでも良いですし、パソコンが得意な方はExcelやGoogleスプレッドシートを使うと便利です。
2.3 当日のタイムテーブル作成術
さあ、準備もいよいよ大詰めです。忘年会当日をスムーズに進行させるために、簡単なタイムテーブル(進行表)を作っておきましょう。きっちりとしたものである必要はありません。「何時ごろに何をするか」という目安が書かれているだけで、幹事としての心の余裕が生まれます。
司会進行役を他の人にお願いする場合や、上司に挨拶を依頼する場合には、このタイムテーブルを事前に共有しておくと、お互いに安心して当日を迎えられます。当日の流れを具体的にイメージしながら、楽しい時間配分を考えてみてください。
| 時間 | 内容 | 担当者・メモ |
|---|---|---|
| 19:00 | 開会の挨拶 | 司会者:〇〇さん |
| 19:05 | はじめの挨拶 | 〇〇部長 |
| 19:10 | 乾杯の音頭 | 〇〇課長 |
| 19:15 | 歓談・食事 | BGMを流すのを忘れずに。 |
| 20:00 | 余興・ゲーム | 景品の準備をしておく。 |
| 20:45 | 締めの挨拶 | 〇〇さん |
| 20:55 | 一本締め(または三本締め) | 締めの挨拶に続いて行う。 |
| 21:00 | 閉会・お見送り | 忘れ物がないか声をかける。二次会の案内もこの時に。 |
3. 忘年会が盛り上がる出し物・余興・ゲーム
忘年会の企画で、幹事さんが一番頭を悩ませるのが「出し物」や「ゲーム」かもしれませんね。でも、大丈夫。みんなで一緒に笑い合える時間があれば、その忘年会はきっと大成功です。ここでは、準備が簡単で、年齢や役職に関係なく誰もが楽しめる出し物やゲーム、そして場が盛り上がる景品選びのコツをご紹介します。素敵な思い出作りの参考にしてくださいね。

3.1 【鉄板】会社でウケる余興と出し物
余興や出し物は、忘年会の雰囲気を一気に華やかにしてくれます。あまり難しく考えず、参加者みんなが主役になれるような、心温まる企画を選んでみませんか。
今年を振り返るスライドショー
一年間の思い出の写真を集めて、BGMと共にスライドショーで上映するのはいかがでしょう。新商品発表の舞台裏、社員旅行での笑顔、何気ない日常の一コマなど、写真と共に一年を振り返ることで、会場に一体感が生まれて感動的な雰囲気に包まれます。準備も比較的簡単で、誰かの負担になりすぎないのも嬉しいポイントです。
会社やメンバーにまつわるクイズ大会
「部長が今年一番熱中した趣味は?」「〇〇さんの入社当時のニックネームは?」など、会社やメンバーに関するクイズは、内輪ネタで盛り上がること間違いなしです。チーム対抗戦にすれば、自然と会話も弾みます。スマートフォンで使える早押しボタンアプリなどを使うと、テレビ番組のような臨場感が出てさらに楽しめますよ。
プロジェクションマッピング
最近では、家庭用の小さなプロジェクターでも手軽に楽しめるプロジェクションマッピングのソフトがあります。会社のロゴや、その年を象徴するキーワードなどを壁に映し出すだけでも、ぐっと特別感が増します。少し凝った演出で、参加者をあっと驚かせてみてはいかがでしょうか。
3.2 【簡単】チーム対抗で楽しめるゲーム
個人で競うゲームも良いですが、チームで協力するゲームは自然とコミュニケーションが生まれ、部署や年代の垣根を越えて仲良くなるきっかけになります。ここでは、ルールがシンプルで誰でもすぐに参加できる、おすすめのチーム対抗ゲームをご紹介します。
| ゲーム名 | 簡単なルール | 準備するもの | 盛り上がるポイント |
|---|---|---|---|
| 絵しりとり | 言葉の代わりに絵を描いてしりとりをつなげていくゲームです。制限時間内に、チームで何問続けられるかを競います。 | 大きめの紙やホワイトボード、ペン | 絵の上手い下手は関係なく、不思議な絵から生まれる珍回答に会場が笑いの渦に包まれます。 |
| ジェスチャーゲーム | お題を言葉を使わずに身振り手振りで表現し、チームメイトに当ててもらいます。お題は「動物」や「スポーツ」など簡単なものから、「部長の口癖」といった少し難しいものまで幅広く用意すると楽しめます。 | お題を書いたカード | 表現する人のユニークな動きや、回答者の面白い勘違いが続出して、見ているだけでも楽しめます。 |
| 万歩計フリフリ対決 | チームの代表者が体に万歩計をつけ、30秒などの制限時間内にどれだけ数を増やせるかを競います。腕や足、腰など、つける場所を工夫するのも面白いですよ。 | 万歩計 | 必死に体を振る姿がコミカルで、応援にも熱が入ります。運動が苦手な方でも気軽に参加できるのが魅力です。 |
| イントロクイズ | 様々な年代のヒット曲のイントロを流し、曲名を当ててもらいます。昭和の歌謡曲から最新のJ-POPまで、幅広いジャンルの曲を用意するのがポイントです。 | 音楽を再生する機器、スピーカー、曲のリスト | 自分の知っている曲が流れると、思わず口ずさんでしまいます。世代を超えてみんなで一緒に盛り上がれる定番のゲームです。 |
3.3 【必見】忘年会の景品選びのポイント
ゲームや余興をさらに盛り上げてくれるのが、素敵な景品です。景品選びで大切なのは、参加者のみなさんが「欲しい!」と思える魅力的なものと、笑いを誘うユニークなものをバランス良く揃えること。持ち帰りやすさや予算も考えながら、みんなの笑顔を思い浮かべて選んでみましょう。

3.3.1 もらって嬉しい豪華景品
目玉となる豪華景品は、忘年会のクライマックスを飾る重要な役割を果たします。自分ではなかなか手が出ないけれど、もらったら暮らしが豊かになるような、そんな「ちょっと贅沢」な品物が喜ばれる傾向にあります。
- グルメギフト券・お食事券: 有名レストランのペアお食事券や、産地直送のお取り寄せグルメカタログギフトは、誰が当たっても嬉しい定番の人気景品です。
- 人気の小型家電: 全自動コーヒーメーカーや電気圧力鍋、ハンディマッサージャーなど、日々の暮らしを少し楽にしてくれる家電は、実用性も高く喜ばれます。
- 体験型ギフト: 日帰り温泉のペアチケットや、テーマパークの入場券など、「楽しい時間」をプレゼントするのも素敵ですね。
- 商品券・ギフトカード: 好きなものを選べる商品券やネット通販のギフトカードは、何が当たるかわからないドキドキ感はありませんが、堅実で満足度の高い景品です。
3.3.2 笑いが取れるユニークな景品
豪華景品の中にいくつかユニークな景品を混ぜ込むと、会場の雰囲気が和んで会話のきっかけにもなります。ただし、ウケを狙いすぎて、もらった人が困ってしまうようなものは避けましょう。クスッと笑える、心遣いの感じられる品物選びが大切です。
- 巨大なお菓子: 子どもの頃に夢見たような、大きな袋に入った駄菓子の詰め合わせや、巨大なチョコレートなどは、見た目のインパクトで盛り上がります。
- 面白いパッケージの日用品: 有名人の顔がプリントされたフェイスパックや、お札の柄のタオルなど、実用的でありながら遊び心のあるアイテムは話の種になります。
- 〇〇券: 「部長とランチに行ける券」「専務がカラオケで一曲歌ってくれる券」など、会社ならではの手作りチケットは、お金では買えない特別な景品として思い出に残ります。
- ご当地レトルトカレーセット: 全国の珍しいご当地カレーの詰め合わせなど、少し変わった食品セットも「次はどれを食べようか」と選ぶ楽しみがありますね。
4. そのまま使える忘年会の挨拶例文集
忘年会の挨拶、頼まれると少し緊張してしまいますよね。でも、大丈夫。大切なのは、長々と話すことではなく、一年を締めくくる感謝の気持ちと、来年への希望を伝えることです。ここでは、どんな立場の方でもそのまま使える挨拶の例文と、心に響くスピーチのコツをわかりやすくご紹介します。これさえ読めば、自信を持って挨拶に臨めますよ。
4.1 立場別の挨拶のポイント
挨拶は、話す人の立場によって少しずつ内容が変わってきます。それぞれの役割に合わせたポイントを押さえることで、より心のこもったスピーチになります。ここでは代表的な立場ごとのポイントをまとめてみました。
| 立場 | 挨拶のポイント | 話の長さの目安 |
|---|---|---|
| 上司・役員 | 一年間の会社の業績や頑張りを振り返り、社員全員への感謝と労いの言葉を伝えます。未来に向けた前向きなメッセージで締めくくると、場が引き締まります。 | 2〜3分程度 |
| 幹事 | まずは、会に参加してくれたことへの感謝を伝えます。そして、会の趣旨を簡単に説明し、「一緒に楽しみましょう!」という明るい雰囲気を作ることが大切です。 | 1分程度 |
| 若手社員 | 挨拶役に抜擢されたことへの感謝を述べ、今年一年で学んだことや成長できたことなどをフレッシュに話しましょう。謙虚さと元気の良さが好印象につながります。 | 1〜2分程度 |
4.2 開会の挨拶と乾杯の音頭
さあ、いよいよ忘年会の始まりです。最初の挨拶は、会の雰囲気を決める大切な役割があります。ここでは、場を和ませ、盛り上げるための開会の挨拶と乾杯の音頭の例文をご紹介します。
4.2.1 【幹事・司会者向け】シンプルな開会の挨拶
皆さま、本日はお忙しい中、忘年会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。
幹事を務めさせていただきます、〇〇部の〇〇です。
今年も残すところあとわずかとなりました。皆さま、この一年、本当にお疲れ様でした。
今夜は仕事のことは一旦忘れて、美味しいお酒とお料理を囲みながら、楽しいひとときを過ごしたいと思います。
短い時間ではございますが、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。
4.2.2 【上司向け】乾杯の挨拶
ただいまご紹介にあずかりました、〇〇部の〇〇です。
僭越ながら、乾杯の音頭をとらせていただきます。
皆さん、この一年、本当にお疲れ様でした。今年も皆さんの頑張りのおかげで、素晴らしい一年となりました。心から感謝しています。
来年も皆さんと一緒に、さらに良い年を迎えられることを願っております。
それでは、今年一年の皆さんの頑張りと、来年のさらなる飛躍を祈念しまして、乾杯!
(全員で)乾杯!
4.3 締めの挨拶(一本締め・三本締め)
楽しい時間もあっという間に過ぎ、いよいよお開きの時間です。締めの挨拶は、会を気持ちよく終え、参加者全員に「良い会だったな」と思ってもらうための大切な締めくくり。感謝の気持ちを込めて、明るく締めましょう。
4.3.1 【上司・役職者向け】締めの挨拶
皆さま、本日は誠にありがとうございました。宴もたけなわではございますが、お開きの時間となりましたので、締めの挨拶をさせていただきます。
こうして皆さんと美味しいお酒を酌み交わし、今年一年の労をねぎらうことができ、大変嬉しく思います。
この会を準備してくれた幹事の皆さん、本当にありがとうございました。皆さま、どうぞ幹事の方々に大きな拍手をお願いいたします。(拍手)
来年も健康に気をつけて、また元気な顔で会いましょう。
それでは、皆さまの今後のご健勝と会社の益々の発展を祈念いたしまして、一本締めで締めたいと思います。お手を拝借!
(よーぉ、パン!)
ありがとうございました。
4.3.2 手締めの種類とやり方
締めの挨拶でよく行われる「手締め」。場を一つにまとめ、会をきれいに締めくくる日本の素敵な習慣です。代表的な「一本締め」と「三本締め」の違いとやり方を知っておくと、いざという時に役立ちますよ。
| 種類 | やり方 | 意味合い・使う場面 |
|---|---|---|
| 一本締め | 「お手を拝借。よーぉ…(ひと呼吸おいて)…パン!」と、1回だけ手を打ちます。 | 「参加者全員で手締めを1回行う」という意味で、最も一般的な手締めです。会社の忘年会や飲み会など、様々な場面で使われます。 |
| 三本締め | 「お手を拝借。よーぉ…(ひと呼吸おいて)…パパパン パパパン パパパン パン」のリズムで手を打ちます。これを3回繰り返します。 | より丁寧で正式な手締めです。会社の創立記念式典や株主総会、結婚式など、おめでたい席や公式な場で使われることが多いです。 |
ちなみに、1回だけ「パン!」と手を打つのは「一丁締め」と呼ばれ、一本締めとは区別されることもあります。地域によっても習慣が異なる場合がありますが、忘年会では元気よく「一本締め」で締めくくるのが一般的ですね。
5. まとめ
一年の締めくくりに開かれる忘年会。この記事では、その意味や由来といった基本から、幹事を任されたときに役立つ企画や準備の進め方、会を盛り上げる余興や挨拶の例文まで、幅広くご紹介してまいりました。
忘年会とは、単に年末の飲み会を指すのではなく、共に一年を過ごした仲間と互いの労をねぎらい、心新たに新年を迎えるための大切な節目です。準備は大変なこともあるかもしれませんが、参加する方々の顔を思い浮かべながら心を込めて準備をすれば、その想いはきっと伝わることでしょう。
このガイドが、幹事という大役を担うあなたの心強い味方となり、関わるすべての人にとって忘れられない、あたたかな時間をつくるための一助となれば幸いです。皆様にとって、今年一年を笑顔で締めくくれるような、素敵な忘年会となりますように。












コメント