「もしも」の備え、気になりつつも特別な準備は大変…と感じていませんか。実は、賢い防災はいつものお買い物ついでに始められます。この記事では、普段使うものを少し多めに備える「ローリングストック」の基本から、スーパーで揃う食品・日用品の具体的なリスト、無理なく続く収納のコツまで丁寧に解説します。無駄なく、暮らしの中にそっと安心を取り入れるヒントがわかりますよ。
1. ローリングストックとは?防災備蓄との違いをわかりやすく解説
「防災」と聞くと、なんだか大変そうで、何から手をつけていいかわからない…と感じていませんか。そんな方にこそ知っていただきたいのが「ローリングストック」という考え方です。特別な準備は必要なく、いつものお買い物のついでに始められる、賢くてやさしい備えの方法なんですよ。
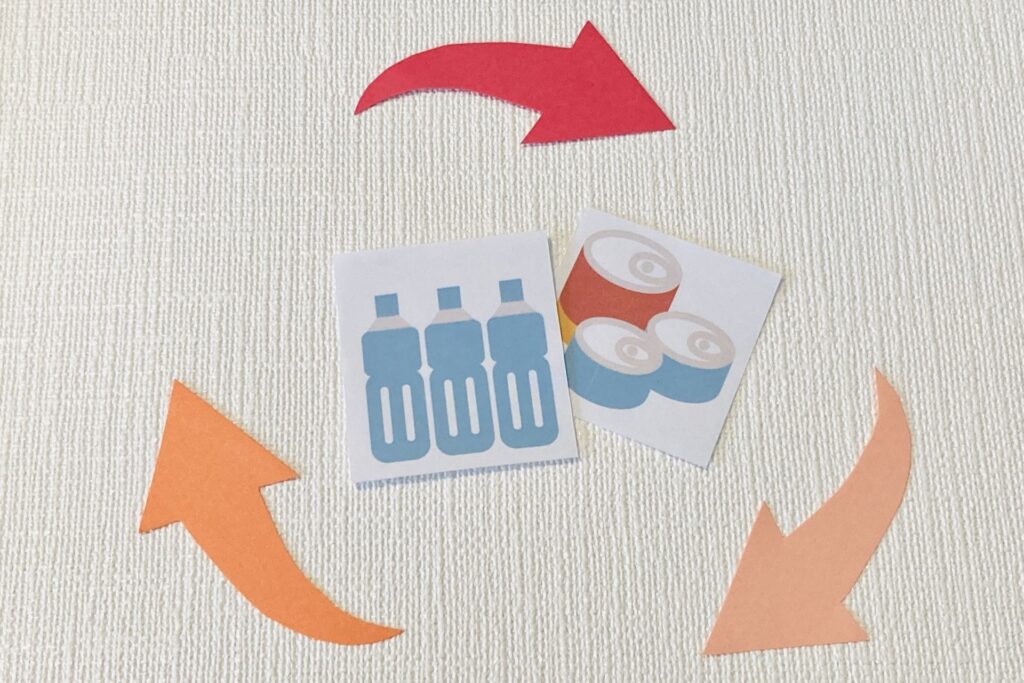
1.1 ローリングストックの基本的な考え方
ローリングストックとは、普段の暮らしで使う食料品や日用品を少しだけ多めに買っておき、賞味期限の古いものから使い、使った分だけ新しく買い足していくという、とてもシンプルな備蓄方法です。「回しながら(Rolling)備蓄する(Stock)」という名前の通り、常に一定量の備えが家にある状態を保ちます。
例えば、いつも食べているレトルトカレーを考えてみましょう。普段は2つ買っているとしたら、それを4つに増やします。そして、1つ食べたら、次のお買い物の際にまた1つ買い足すのです。こうすることで、ご家庭には常に新しいものと少し前のものが混ざり合った状態で、一定量のカレーが備蓄されていることになります。この繰り返しが、いざという時の安心につながるのですね。
1.2 一般的な防災備蓄とローリングストックの違い
これまでの防災備蓄というと、長期保存できる特別な非常食をセットで買い、押入れの奥にしまい込んでおく、というイメージが強かったかもしれません。そして、気づいた時には賞味期限が切れてしまっていた…なんて、ちょっぴり残念な経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ローリングストックは、そんな「しまいっぱなし」の備蓄とは少し違います。一番の違いは、「日常」と「非常時」の垣根を取り払う点にあります。下の表で、それぞれの違いを比べてみましょう。
| ローリングストック | 一般的な防災備蓄 | |
|---|---|---|
| 食品・日用品 | 普段から使い慣れた、食べ慣れたもの | 長期保存用の特別な非常食が中心 |
| 管理方法 | 日常的に消費し、使った分を買い足す | 特定の場所に保管し、定期的に期限を確認・入れ替え |
| 賞味期限 | 消費の循環が早いため、期限切れの心配が少ない | しまい忘れによる期限切れのリスクがある |
| 始めやすさ | いつもの買い物の延長で、気軽に始められる | 何を揃えるか計画が必要で、少し手間がかかる |
このように、ローリングストックは、特別な準備ではなく、いつもの暮らしの延長線上にある備えの方法です。農林水産省も、家庭での食料品備蓄のヒントとしてこの方法を推奨しています(災害時に備えた食品ストックガイド)。無理なく、無駄なく。わたしたちの毎日にそっと寄り添ってくれる、新しい備えの形を始めてみませんか。
2. ローリングストックを始めるメリットと無理なく続けるコツ
「防災のための備蓄」と聞くと、少し大変そうに感じてしまうかもしれませんね。でも、ローリングストックは、もしもの備えが日々の暮らしをちょっと豊かにしてくれる、そんな素敵な習慣なんです。ここでは、ローリングストックの嬉しいメリットと、気負わずに楽しく続けるためのヒントをご紹介します。
2.1 普段の生活にも役立つローリングストックのメリット
ローリングストックは、特別な防災グッズを揃えることとは少し違います。普段から食べているもの、使っているものを少し多めに買っておくだけ。だからこそ、災害時だけでなく、私たちの毎日の暮らしにもたくさんの良いことがあるんですよ。
2.1.1 メリット1:いざという時の「食」の安心につながる
災害はいつ起こるかわかりません。そんな時、食べ慣れたいつもの味があるだけで、心はぐっと落ち着くものです。特に、環境の変化に敏感なお子さんやご高齢の家族がいるご家庭では、普段の食事が何よりの安心材料になります。特別な非常食だけでなく、お気に入りのレトルトカレーや好きなお菓子がそばにある。それがローリングストックの大きな魅力です。
2.1.2 メリット2:食品ロスを減らして、お財布にもやさしい
「防災用に買った食品の、賞味期限が切れていた…」なんて経験はありませんか?ローリングストックは、古いものから順番に食べて、食べた分だけ買い足していく方法です。そのため、うっかり賞味期限を切らしてしまう「食品ロス」を自然と防ぐことができます。また、お米やパスタ、缶詰などが安い時に少し多めに買っておけば、日々の食費の節約にもつながり、家計の助けにもなりますね。
2.1.3 メリット3:忙しい日や急な体調不良の時のお守りになる
ローリングストックが活躍するのは、災害の時だけではありません。「今日は疲れてごはんを作る気力がないな」「急な発熱で買い物に行けない…」そんな日々のちょっとした「困った」にも、やさしく寄り添ってくれます。家にストックがあるとわかっているだけで、心に余裕が生まれます。慌てて買い物に走る必要がなくなり、時間も気持ちもゆったりと過ごせるようになりますよ。
2.2 失敗しないための管理方法と続けるコツ
「管理が面倒になって、結局やめてしまった」という声も耳にします。でも、大丈夫。ほんの少しの工夫で、誰でも無理なく続けることができます。大切なのは、完璧を目指さず、ご自身の暮らしに合った方法を見つけることです。
2.2.1 まずは「見える化」で在庫を把握する
何をどれだけ持っているか、まずは知ることから始めましょう。難しく考える必要はありません。キッチンの引き出しや棚の一角を「ローリングストックコーナー」に決めて、そこにまとめて置くだけでも立派な「見える化」です。在庫の量がひと目でわかると、消費や買い足しの計画も立てやすくなります。
2.2.2 自分に合った管理方法を見つける
在庫の管理方法は、ご自身が一番やりやすい方法でかまいません。いくつか代表的な方法をご紹介しますね。
| 管理方法 | やり方 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| 手書きリスト法 | ノートやメモ帳、冷蔵庫に貼ったホワイトボードなどに、食品名と賞味期限、数量を書き出す方法です。 | スマートフォンなどの操作が苦手な方や、自分の手で書くことで記憶したい方。 |
| スマホアプリ活用法 | 在庫管理や賞味期限管理のアプリを使います。商品のバーコードを読み取るだけで登録できるものもあり、手軽です。 | スマートフォンを日常的に使いこなしている方や、外出先でも在庫を確認したい方。 |
| 収納ケース活用法 | 中身の見える透明なケースや、カゴにざっくりと種類分けして収納する方法です。リスト管理が面倒な方でも直感的に在庫を把握できます。 | 細かく管理するのが苦手な方や、まずは手軽に始めたい方。 |
2.2.3 無理なく続けるための3つのコツ
最後に、ローリングストックを「特別なこと」ではなく「普段の習慣」にするためのコツを3つお伝えします。
- ルールは「ゆるやか」に
「毎月1日に必ずチェックする!」と厳しく決めすぎると、できなかった時に気持ちが重くなってしまいます。「お給料日後の最初の週末に」など、ご自身の生活サイクルに合わせて、少し余裕のあるルールにするのが長続きの秘訣です。 - 「もしも」ではなく「いつも」を意識する
備蓄している缶詰やレトルト食品を、月に一度は食卓に出す「お楽しみデー」を作ってみませんか。普段から味に親しんでおくことで、いざという時も安心して食べられますし、家族のお気に入りの味を見つけるきっかけにもなります。 - まずは「水」1本からでも
最初からすべてを完璧に揃えようとすると、気負ってしまいます。まずはいつも飲んでいるペットボトルの水を1本多めに買う、ということから始めてみましょう。ひとつできたら、次はパックごはん、次は好きな缶詰、というように、少しずつ仲間を増やしていくような気持ちで楽しむことが、何よりも大切なポイントですよ。
3. 【食品編】スーパーで揃うローリングストックにおすすめのリスト
「いざという時のために、何か備えなくちゃ」と思ってはいても、特別な非常食を揃えるのは少し大変に感じますよね。でも、ご安心ください。ローリングストックは、いつものスーパーでのお買い物のついでに、無理なく始められるのが素敵なところ。普段の食事にも使えるおいしいものを選んで、暮らしの中にそっと備えを溶け込ませてみませんか。ここでは、毎日の食卓でも活躍する、おすすめの食品をリストアップしてご紹介します。
3.1 主食になるもの(パックごはん、パスタ、カップ麺)
まずは、私たちの元気の源になる主食から。災害時でも、温かいごはんや麺類が食べられると、心も体もほっと温まります。調理が簡単なものや、そのままでも食べられるものを選んでおくと、いざという時にとても心強いですよ。
| 食品の種類 | 選び方のポイントとコツ |
|---|---|
| パックごはん・アルファ化米 | 電子レンジやお湯で温めるだけですぐに食べられる手軽さが魅力です。白米だけでなく、玄米や五穀米など、普段から食べ慣れているものを選ぶと、日常の食卓でも消費しやすくなります。 |
| 乾麺(パスタ・そうめん・うどん) | 軽くてかさばらず、長期保存に向いています。様々なソースと組み合わせれば、飽きずに楽しめますね。調理には水と熱源が必要になるので、カセットコンロと一緒に備えておくと安心です。 |
| カップ麺・袋麺 | お湯を注ぐだけで手軽に食べられる、心強い味方です。好きな味のものをいくつかストックしておけば、災害時の不安な気持ちを和らげる「お守り」のような存在にもなってくれます。 |
| その他(シリアル・餅・ホットケーキミックス) | 調理不要で牛乳や豆乳をかけるだけで食べられるシリアルは、忙しい朝の味方にもなります。お餅やホットケーキミックスも、腹持ちが良く、おやつにもなるのでおすすめです。 |
3.2 主菜になるもの(レトルトカレー、パスタソース、缶詰)
主食だけでは、どうしても栄養が偏りがち。お肉やお魚を使った主菜があれば、食事の満足感がぐっと高まります。パックごはんやパスタにかけるだけ、あるいは開けてそのまま食べられるものを用意しておくと、調理の負担も少なく済みます。
特に注目したいのが、「温めなくてもおいしく食べられる」と書かれたレトルト食品です。電気やガスが使えない状況でも、そのままごはんにかけるだけで立派な一品になりますから、パッケージをよく見て選んでみてくださいね。
| 食品の種類 | 選び方のポイントとコツ |
|---|---|
| レトルト食品(カレー・丼の具など) | カレーやシチュー、牛丼の具など、種類が豊富で選ぶのも楽しいですね。野菜がごろっと入っているものを選ぶと、栄養バランスも少し整います。 |
| パスタソース | パスタに和えるだけでなく、ごはんにかけてドリア風にしたり、パンにつけたりと、意外なアレンジが楽しめる万能選手。ミートソースやナポリタンなど、ご家族が好きな定番の味を揃えておくと良いでしょう。 |
| 缶詰(さば・いわし・ツナ・焼き鳥など) | 調理いらずで、開けたらすぐに食べられる優れものです。さばの味噌煮やいわしの蒲焼のように味付けされたものは、そのまま立派なおかずに。ツナ缶やオイルサーディンは、油も貴重なエネルギー源や調味料として活用できます。 |
3.3 副菜や間食になるもの(フリーズドライスープ、お菓子)
主食と主菜に、もう一品。温かい汁物や、ほっと一息つけるお菓子があると、食事が豊かになるだけでなく、心の栄養にもなります。特に災害時は、知らず知らずのうちに心も体も疲れてしまうもの。「好きなものを食べる時間」が、明日への活力につながります。
野菜不足を補うための野菜ジュースや、気持ちを和らげる甘いお菓子など、「これも備えになるんだ」という視点でスーパーを眺めてみると、新しい発見があるかもしれません。
| 食品の種類 | 選び方のポイントとコツ |
|---|---|
| フリーズドライ・インスタントの汁物 | お湯を注ぐだけで、温かいお味噌汁やスープが楽しめます。わかめや野菜がたくさん入ったものを選べば、手軽に栄養をプラスできます。体を温めてくれる一杯は、心も落ち着かせてくれますよ。 |
| 野菜・果物の缶詰、野菜ジュース | 不足しがちなビタミンや食物繊維を補うのに役立ちます。コーンやミックスビーンズの缶詰は、スープやサラダに加えるだけで彩りも豊かになります。日持ちのする野菜ジュースも、手軽な栄養補給におすすめです。 |
| お菓子・嗜好品 | チョコレートやクッキー、飴、おせんべいなど、普段から食べ慣れているお気に入りのお菓子を用意しておきましょう。個包装のものは、分けやすく衛生的で便利です。ようかんは長期保存が可能で、手軽なエネルギー補給にもなります。 |
| その他(ふりかけ・海苔・梅干し) | ごはんのお供があれば、食欲がない時でも不思議とごはんが進みます。昔ながらの梅干しは、日持ちがするだけでなく、気分をさっぱりさせてくれる効果も期待できますね。 |
4. 【飲料・非常食編】いざという時に備えるローリングストック
食品と同じくらい、いえ、それ以上に大切なのが飲み水と、いざという時のための特別な食事です。ここでは、命を守るための飲料水と、日常の食卓にも取り入れやすい「非常食」について、詳しく見ていきましょう。少し備えておくだけで、心の余裕が生まれますよ。
4.1 備蓄の基本となる飲料水
私たちの体にとって、お水はなくてはならないもの。災害時に水道が止まってしまった時のために、飲料水は必ず備えておきたいアイテムの筆頭です。「最低でも3日分、できれば1週間分」を目安に準備するのが推奨されています。
農林水産省のガイドラインによると、大人1人あたり1日3リットルが目安とされています。この量には、飲み水だけでなく、簡単な調理に使う水も含まれています。ご家族の人数に合わせて、必要な量を計算してみましょう。
4.1.1 家族の人数別|飲料水備蓄量の目安(3日分)
| 家族の人数 | 必要な水の量 | 2Lペットボトルの本数 |
|---|---|---|
| 1人暮らし | 9リットル | 5本 |
| 2人家族 | 18リットル | 9本 |
| 3人家族 | 27リットル | 14本 |
| 4人家族 | 36リットル | 18本 |
ペットボトルの水は、賞味期限が長いものが多いのでローリングストックにぴったり。普段から箱買いしておき、手前のものから飲んで、飲んだ分だけ新しいものを奥に補充するというルールを決めておくと、無理なく続けられます。賞味期限が5年以上の「長期保存水」も市販されていますが、まずは普段飲んでいるミネラルウォーターから始めるのが手軽でおすすめです。
また、水だけでなく、お茶や野菜ジュース、経口補水液なども少し備えておくと、水分補給の選択肢が広がって安心ですね。
4.2 日常でも消費しやすい長期保存食
「非常食」と聞くと、乾パンのような特別なものを想像するかもしれません。でも最近は、普段の食事と変わらないくらい美味しくて、日常でも食べたくなるような長期保存食がたくさん登場しているんですよ。
災害時は、心も体も疲れてしまうもの。そんな時だからこそ、「美味しい」と感じる食事が、何よりの元気の源になります。賞味期限が近づいたら、週末のランチや、ちょっと疲れて食事の準備が大変な日に活用してみましょう。実際に食べて味を知っておくことも、いざという時の安心につながります。
4.2.1 おすすめの長期保存食リスト
- アルファ米:お湯や水を注ぐだけで、ふっくら美味しいごはんが食べられます。白米だけでなく、五目ごはんやわかめごはんなど種類も豊富。尾西食品のシリーズは特に人気があります。
- 長期保存できるパン:缶詰やパウチに入ったパンは、開けてすぐに食べられるのが魅力。「パン・アキモト」のパンの缶詰や、コモの「ロングライフパン」などは、しっとりとしていて日常のおやつにもぴったりです。
- レトルトのおかず:温めずにそのまま食べられるものが便利です。グリコの「常備用カレー職人」や、杉田エースの「IZAMESHI(イザメシ)」シリーズは、おかずの種類が豊富でおすすめです。
- 栄養補助食品:井村屋の「えいようかん」は、手軽にカロリー補給ができる羊羹で、5年間の長期保存が可能です。甘いものは心を和ませてくれますね。
- 野菜ジュース:カゴメの「野菜一日これ一本 長期保存用」のように、賞味期限が5.5年と長いものもあります。災害時に不足しがちな野菜の栄養を補うのに役立ちます。
これらの長期保存食を、いつもの食品ストックに少しだけプラスしてみてください。賞味期限を定期的にチェックして、古いものから美味しくいただく。この繰り返しが、無理なく続けるローリングストックの秘訣です。
5. 【日用品編】見落としがち?ローリングストックしておきたいアイテム
お水や食べ物の備えは意識していても、意外と忘れがちなのが日用品です。災害は突然やってきます。いざという時に「あれがなくて困った…」なんてことにならないように、日用品もしっかり備えておきましょう。ここでは、普段の暮らしの延長で気軽に始められる、日用品のローリングストックリストをご紹介しますね。
5.1 衛生用品(トイレットペーパー、ウェットティッシュ)
電気や水道が止まってしまった時、心と体の健康を保つために欠かせないのが衛生用品です。特に、清潔を保つためのアイテムは、感染症の予防にもつながる大切な備えになります。普段使っているものを少し多めに買い置きしておくだけで、もしもの時の大きな安心につながりますよ。
| アイテム名 | 備蓄の目安とポイント |
|---|---|
| トイレットペーパー・ティッシュペーパー | かさばりますが、ないと本当に困るものです。いつもより1パック多めにストックしておくことを習慣にしましょう。水に溶けるティッシュも便利です。 |
| ウェットティッシュ・からだ拭きシート | 断水でお風呂に入れない時や、手を洗えない時に大活躍します。アルコール入りの除菌タイプと、お肌にやさしいノンアルコールタイプがあると使い分けができて便利です。 |
| 生理用品・おりものシート | 災害時でも生理はやってきます。入手が困難になる場合があるので、最低でも2周期分あると安心です。デリケートなことだからこそ、ご自身に合ったものを備えておきましょう。 |
| 大人用紙おむつ・介護用品 | ご家族に介護が必要な方がいらっしゃる場合は、必需品です。普段お使いのものを、切らさないように多めに備蓄しておきましょう。 |
| マスク・手指消毒液 | 避難所など、人が集まる場所での感染症対策に。個包装のマスクは持ち運びにも便利です。 |
| 歯磨きシート・ドライシャンプー | 水が使えない状況でも、お口や髪をさっぱりさせることができます。気分転換にもなり、心身のリフレッシュに役立ちます。 |
5.2 生活用品(カセットコンロ、乾電池、ラップ)
ライフラインが止まってしまった暮らしを支えてくれるのが、こまごまとした生活用品です。温かい食事がとれたり、明かりがあったりするだけで、不安な気持ちが和らぐものです。ここでは、特に役立つアイテムと、ちょっとした活用術もあわせてご紹介します。
| アイテム名 | 備蓄の目安とポイント |
|---|---|
| カセットコンロ・ガスボンベ | 電気や都市ガスが止まっても、温かい食事を作ったり、お湯を沸かしたりできます。ボンベは1本で約60分が燃焼時間の目安です。ご家族の人数に合わせて、1週間分程度(7本〜)を備えておくと安心です。使用期限も確認しておきましょう。 |
| 乾電池・モバイルバッテリー | 懐中電灯やラジオ、スマートフォンの充電に必須です。単1から単4まで、ご家庭で使う機器に合わせたサイズを揃えておきましょう。スマートフォンの充電用に、大容量のモバイルバッテリーも一つあると心強い味方になります。 |
| 食品用ラップフィルム | お皿に敷いて使えば、水が貴重な時の洗い物を減らせます。止血や防寒対策として体に巻くなど、防災の知恵としても万能なアイテムです。 |
| ポリ袋・ごみ袋 | 食材を混ぜたり、お米を炊いたりする「ポリ袋調理」に役立ちます。ごみ袋は、簡易トイレや雨具、防寒着代わりにもなる優れものです。様々なサイズを用意しておくと重宝します。 |
| 懐中電灯・LEDランタン | 停電時の明かりの確保は、安全のために最も重要です。枕元や玄関など、すぐに手の届く場所に置いておきましょう。両手が使えるヘッドライトも便利ですよ。 |
| 使い捨てカイロ | 冬場の災害では、暖をとる手段として非常に役立ちます。貼るタイプと貼らないタイプの両方があると、用途に応じて使い分けができます。 |
これらの日用品は、特別なものではなく、ほとんどがスーパーやドラッグストアで手軽に購入できるものばかりです。お買い物の際に「いつものストックに、もう一つだけプラスする」という気持ちで、少しずつ備えてみてはいかがでしょうか。小さな心がけが、いざという時のあなたと大切なご家族を守る大きな力になりますよ。
6. ローリングストックの収納術!場所別のアイデアとコツ
せっかく揃えた食品や日用品も、いざという時にどこにあるかわからなかったり、賞味期限が切れてしまってはちょっぴり残念ですよね。でも、ご安心ください。ローリングストックの収納は、特別な場所も難しいテクニックも必要ないんですよ。「しまい込む」のではなく、暮らしの中で「循環させる」のがポイント。いつもの暮らしの中に、無理なく取り入れられる収納のコツを、場所別にご紹介しますね。
6.1 キッチン周りの収納アイデア
毎日使うキッチンは、食品の管理がしやすく、ローリングストックの基本となる場所です。調理のついでに在庫を確認したり、賞味期限をチェックしたりと、自然に管理できるのが嬉しいですね。ここでの合言葉は「見える化」と「先入れ先出し」。手前のものから使い、新しく買ってきたものは奥に補充する、この簡単なルールを守るだけで、食品ロスを防ぎながら上手に備蓄を回せますよ。
収納ケースやカゴを使って、「ごはん類」「麺類」「缶詰」のように種類ごとに分けておくと、見た目もすっきりして、どこに何があるか一目でわかります。無印良品やニトリ、100円ショップなどで手に入るファイルボックスは、レトルトパウチを立てて収納するのにぴったり。ぜひ試してみてくださいね。
| 収納場所 | 収納におすすめのもの | コツ・ポイント |
|---|---|---|
| シンク下・コンロ下 | 飲料水、缶詰、瓶詰、カセットボンベなど重いもの | 重いものは低い場所に置くのが安全です。キャスター付きの台に乗せると、奥のものも楽に取り出せます。 |
| 吊り戸棚・パントリー | パックごはん、パスタ、カップ麺、レトルト食品、フリーズドライ食品、お菓子など軽いもの | 取っ手付きの収納ボックスを使うと、高い場所でも出し入れが簡単。中身がわかるようにラベルを貼っておくと便利です。 |
| 冷蔵庫・野菜室 | 長期保存できる野菜(じゃがいも、玉ねぎなど)、お米、開封後の調味料 | お米は密閉容器に入れて冷蔵庫で保存すると、鮮度が長持ちします。ローリングストック用のスペースを一段決めておくと管理しやすくなります。 |
6.2 クローゼットや押し入れを活用した分散備蓄
もしもの時、いつもいる場所にすぐに戻れるとは限りません。また、地震などでキッチンの棚が倒れてしまう可能性も考えておきたいところ。そんな時に備えて、家の中のいくつかの場所に分けて置いておく「分散備蓄」という考え方が、あなたとご家族を守るお守りになります。
キッチンに収まりきらない食品や、トイレットペーパーなどの日用品は、クローゼットや押し入れの一部を活用してみましょう。普段はあまり使わないスペースを「もしもの時の安心スペース」に変えるだけで、心にぐっとゆとりが生まれますよ。
押し入れの天袋には軽いティッシュペーパーやウェットティッシュ、ベッドの下の収納ケースには飲料水やカセットコンロなど、重いものは下に、軽いものは上に置くのが収納の基本です。こうすることで、地震の時も安全ですね。どこに何をしまったか忘れないように、簡単なリストを作って収納の扉の裏などに貼っておくと、いざという時も慌てずに済みます。
6.2.1 分散備蓄の場所とアイテムの例
- クローゼットの上段:トイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、ラップ、アルミホイルなど軽くてかさばるもの
- 押し入れの奥や下段:飲料水のストック、カセットコンロ・ボンベ、長期保存できるお菓子
- ベッドの下:収納ケースに入れた飲料水、非常食、乾電池、簡易トイレ
- 玄関の収納:すぐに持ち出せる防災リュックと一緒に、靴の中に敷く中敷きやマスク、携帯用アルコールジェルなどを少し
このように、家の中のちょっとしたスペースを活用することで、無理なく、暮らしの動線を邪魔することなく、賢く備えることができます。まずは一か所から、試してみてはいかがでしょうか。
7. まとめ
ローリングストックは、特別な準備ではなく、いつもの暮らしの延長線上にある、心穏やかに過ごすための知恵です。スーパーで少し多めに買った食品や日用品を、古いものから使い、使った分を買い足すだけ。この無理のない習慣が、もしもの時の大きな安心につながります。賞味期限を気にしすぎることもなく、食品ロスを防げるのも嬉しい点ですね。まずはいつものお水や好きな缶詰を一つ多く買うことから、あなたの毎日にそっと安心をプラスしてみませんか。










コメント