ふと気づくとお風呂の隅や窓のパッキンにできている黒カビ。見て見ぬふりをしていると、実は健康にも影響があるかもしれません。この記事では、そんな気になる黒カビの落とし方を場所別に徹底解説します。カビキラーなどの強力な洗剤から重曹を使ったやさしい方法、そして二度と発生させないための予防策まで、ご家庭で実践できる知恵が満載です。頑固なカビの悩みをすっきり解消して、心地よい毎日を送りましょう。
1. 黒カビが発生する原因と放置する健康へのリスク
いつの間にか、お風呂の隅や窓のサッシに現れる黒い点々。それは、ただの汚れではなく「黒カビ」です。見た目が不快なだけでなく、実は私たちの暮らしや健康にも関わっています。まずは、なぜ黒カビが発生してしまうのか、その原因をきちんと知ることから始めましょう。理由がわかれば、効果的な対策も見えてきますよ。

1.1 黒カビの正体と発生する3つの条件
そもそも黒カビとは、空気中に漂っているごくありふれたカビの一種、「クラドスポリウム」などが原因です。このカビが壁や床に根を張り、黒い色素を作り出すことで、私たちの目に見えるようになります。では、どうして家の中に発生してしまうのでしょうか。実は、黒カビが元気に育つためには、3つの条件が揃う必要があるのです。
その3つの条件とは、「温度」「湿度」「栄養」です。まるで植物が育つのに水や光、土が必要なように、カビにも快適な環境があるのですね。下の表で、カビが好む環境を具体的に見てみましょう。
| カビが好む条件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 温度 | 20~30℃くらいの、人が心地よいと感じる暖かい場所を好みます。特に春から秋にかけての室内は、カビにとっても過ごしやすい環境になりがちです。 |
| 湿度 | 湿度70%以上で活動を始め、80%を超えると一気に増えていきます。湯気で湿気がこもりやすいお風呂場や、冬に結露しやすい窓際は、特に注意が必要です。 |
| 栄養 | ホコリ、髪の毛、皮脂、石鹸カスなど、実は家の中にあるほとんどの汚れがカビの栄養源になります。こまめなお掃除が大切な理由がここにあります。 |
この3つの条件が揃いやすい場所、例えばお風呂場やキッチン、結露した窓の周りなどは、黒カビにとって最高の住処となってしまうのです。ひとつでも条件を断ち切ることが、カビの発生を防ぐ第一歩になります。
1.2 黒カビを放置すると危険 アレルギーや喘息の原因に
「少しのカビくらいなら大丈夫」と、見て見ぬふりをしていませんか?実は、黒カビを放置することは、見た目の問題以上に、私たちの健康に良くない影響を及ぼす可能性があります。黒カビは、目に見えないほどの小さな「胞子」を空気中にたくさん飛ばしています。この胞子を吸い込んでしまうことで、様々な体の不調を引き起こすことがあるのです。
具体的には、次のような健康リスクが考えられます。
- アレルギー症状
カビの胞子がアレルゲン(アレルギーの原因物質)となり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといったアレルギー性鼻炎や、目のかゆみ、充血などのアレルギー性結膜炎を引き起こすことがあります。 - 喘息(ぜんそく)
カビの胞子を吸い込むことが、気管支喘息の発作のきっかけになったり、症状を悪化させたりすることが知られています。 - 過敏性肺炎
カビの胞子を繰り返し吸い込むことで、肺がアレルギー反応を起こし、咳や息切れ、発熱といった症状が現れることがあります。特に夏に発生しやすい「夏型過敏性肺炎」は、トリコスポロンというカビが原因のひとつとされています。 - 皮膚のトラブル
アトピー性皮膚炎の方がカビに触れたり、胞子を吸い込んだりすることで、症状が悪化する場合があります。
特に、体の抵抗力が弱い小さなお子様やご高齢の方、もともとアレルギー体質の方は影響を受けやすいため、注意が必要です。大切なご家族の健康を守るためにも、黒カビを見つけたら「汚れ」としてだけでなく、「健康を脅かすもの」として捉え、早めに対処することがとても大切なのですよ。
2. 黒カビの掃除を始める前に知っておくべき準備と注意点
黒カビを見つけると、一刻も早く取り除きたい気持ちになりますよね。でも、その前に少しだけ準備の時間をとりましょう。ご自身の体を守り、安全にお掃除を終えるために、とても大切なことなんですよ。まずは必要なものと、心に留めておいてほしい注意点を確認していきましょうね。
2.1 安全な掃除のための必須アイテム
カビ取り剤は効果が高い分、肌や体に刺激を与えることがあります。また、カビの胞子を吸い込んでしまうのも避けたいもの。お掃除を始める前には、必ず次のアイテムを揃えて、しっかりと体を守ってあげてくださいね。

| アイテム | 必要な理由 |
|---|---|
| ゴム手袋 | 洗剤が直接肌に触れるのを防ぎ、手荒れから守ります。少し厚手のものを選ぶと、より安心です。 |
| マスク | カビの胞子や、洗剤のツンとした臭いを吸い込んでしまうのを防ぎます。 |
| 保護メガネやゴーグル | 洗剤が目にはねてしまうのを防ぎます。特に、天井など自分より高い場所をお掃除する際には必ず着用しましょう。 |
| 長袖・長ズボン | 肌の露出を減らし、洗剤が腕や足に付着するのを防ぎます。汚れても気にならない服装がおすすめです。 |
そして、何よりも大切なのが「換気」です。お掃除を始める前から終えた後まで、必ず窓を2か所以上開けるか、換気扇を回し続けて、お部屋の空気がしっかり入れ替わるようにしてくださいね。
2.2 塩素系洗剤を使う際の絶対的な注意点「混ぜるな危険」
カビ取り剤としてよく使われる塩素系漂白剤。そのパッケージに書かれている「混ぜるな危険」の文字は、誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。これは、命に関わることもある、絶対に守らなくてはならない大切なお約束です。

塩素系の洗剤は、酸性タイプの製品と混ざると、人体に非常に有害な「塩素ガス」が発生します。塩素ガスを吸い込むと、目や喉、呼吸器が激しい刺激を受け、最悪の場合、命を落とす危険性もあります。
| 絶対に混ぜてはいけない組み合わせ | 具体例 |
|---|---|
| 塩素系の洗剤・漂白剤 | カビキラー、キッチンハイター、ドメストなど |
| 酸性タイプの製品 | クエン酸、お酢、一部のトイレ用洗剤(サンポールなど) |
うっかり混ぜてしまわないよう、お掃除の際には一つの洗剤だけを使うように心がけましょう。もし、複数の洗剤を使いたい場合は、一度きれいに水で洗い流し、十分に換気をしてから、時間をあけて使うようにしてくださいね。この点については、消費者庁からも注意喚起がなされていますので、ぜひ一度ご確認ください。(参考:消費者庁「混ぜるな危険!塩素系漂白剤や塩素系洗浄剤を安全に使いましょう!」)
万が一、混ぜてしまって刺激臭がした場合は、すぐにその場から離れて、新鮮な空気を吸い、窓を開けて十分に換気をしてください。目や喉に痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。
3. 効果は?黒カビの落とし方に使う洗剤の種類と特徴
黒カビのお掃除と一言でいっても、使う洗剤はさまざま。場所やカビのしつこさに合わせて、ぴったりのものを選ぶのがきれいへの近道です。ここでは、代表的な4種類の洗剤の特徴を、それぞれの得意なこと、少し気をつけてほしいことと合わせてご紹介しますね。ご自身の暮らしに合った洗剤を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。ぱっと見て比べられるので、参考にしてみてくださいね。
| 洗剤の種類 | 特徴 | こんな方・こんな場所におすすめ |
|---|---|---|
| 塩素系漂白剤 | 殺菌力・漂白力が最も強い。即効性があり、カビの色素を分解して真っ白にしてくれる。 | ゴムパッキンやタイルの目地に根付いた頑固な黒カビを、とにかく早く確実に落としたい方におすすめです。 |
| 酸素系漂白剤 | 発泡する力で汚れを浮かせて落とす。塩素系特有のツンとした臭いがない。効果は穏やか。 | 強い洗剤の臭いが苦手な方や、小さなお子様やペットがいるご家庭でも比較的使いやすいのが魅力です。 |
| 消毒用エタノール | カビを殺菌する効果がある。漂白作用はないため、カビの黒い色素は落とせない。揮発性が高い。 | 発生したばかりの軽いカビの除菌や、お掃除後のカビ予防に手軽に使えます。壁紙などにも。 |
| 重曹・クエン酸 | 環境や人に優しい自然由来の成分。洗浄力はとても穏やか。安心して使える。 | できるだけ化学的な洗剤を使いたくないという方に。ごく初期のカビや日常の予防向きです。 |
3.1 強力な塩素系漂白剤 カビキラーやキッチンハイター
お風呂の黒カビ掃除といえば、多くの方が思い浮かべるのが「カビキラー」などの塩素系漂白剤ではないでしょうか。「次亜塩素酸ナトリウム」を主成分とし、カビの細胞を破壊して根っこから分解する強力な殺菌力と、黒い色素を脱色する漂白効果をあわせ持っています。
ゴムパッキンやタイルの目地に深く根を張ってしまった、しつこい黒カビには最も効果が期待できる洗剤です。スプレーしてしばらく置くだけで、驚くほどきれいになることも。その即効性の高さが最大の魅力ですね。
ただし、効果が強い分、取り扱いには注意が必要です。独特のツンとした刺激臭があるため、必ず窓を開けたり換気扇を回したりと、換気を十分に行いましょう。また、衣類につくと色落ちしてしまうので、お掃除の際は汚れてもよい服装を心がけてくださいね。
3.2 塩素の臭いが苦手な方向けの酸素系漂白剤 オキシクリーンなど
「塩素系洗剤の臭いはどうしても苦手…」という方には、「オキシクリーン」や粉末タイプの「ワイドハイター」などに代表される酸素系漂白剤がおすすめです。主成分は「過炭酸ナトリウム」で、お湯に溶かすと発泡し、その泡の力で汚れを浮かび上がらせて落とします。
塩素系のような刺激臭がなく、環境への負担も少ないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使いやすいのが嬉しいポイント。色柄物の衣類のシミ抜きにも使われるように、素材へのダメージが比較的少ないのも特徴です。
ただし、カビを落とす力は塩素系に比べると穏やか。そのため、黒カビにしっかり密着させるために、お湯で溶いてペースト状にし、キッチンペーパーなどでパックするといったひと手間をかけると、より効果を実感しやすくなりますよ。
3.3 軽い黒カビに効果的な消毒用エタノール
薬局などで手軽に購入できる消毒用エタノールも、カビ対策に役立つアイテムです。エタノールにはカビを殺菌する効果があるため、発生して間もない表面的なカビの除菌に効果を発揮します。
一番の長所は、その手軽さ。スプレーボトルに入れておけば、気になったときにシュッと吹きかけて乾いた布で拭き取るだけでお掃除が完了します。揮発性が高いので二度拭きもいりません。壁紙や木製の家具など、水拭きをしにくい場所のお手入れにも向いています。
注意点として、エタノールには漂白作用はありません。そのため、すでに黒く色素沈着してしまったカビのシミを消すことはできません。あくまでカビの「除菌」と「予防」のためのアイテムと考えるとよいでしょう。また、引火性があるため、火の気のないところで使用してくださいね。
3.4 環境に優しい重曹やクエン酸を使った落とし方
できるだけ自然なものでお掃除を楽しみたい、という方には、重曹やクエン酸が心強い味方になります。どちらも食品にも使われる成分なので、キッチン周りなどでも安心して使えるのが何よりの魅力です。
重曹は、水と混ぜてペースト状にすると、穏やかな研磨剤として使えます。軽いカビ汚れをこすり落とすのに役立ちます。一方、クエン酸は水に溶かしてスプレーすることで、カビの殺菌効果が期待できます。
ただし、これらの洗浄力や殺菌力は、市販のカビ取り剤に比べるとかなり穏やかです。残念ながら、深く根を張った頑固な黒カビを落とすのは難しいかもしれません。ごく初期の小さなカビや、普段のお掃除でカビを予防する、という目的で取り入れるのがおすすめです。暮らしにやさしく寄り添うお掃除方法として、上手に活用してみてくださいね。
4. 【場所別】実践的な黒カビの落とし方
お家の中を見渡してみると、黒カビは実にさまざまな場所に潜んでいます。湿気の多いお風呂場から、意外なエアコンの中まで…。場所や素材によって、効果的なお掃除方法も少しずつ変わってきます。ここでは、場所ごとの特徴に合わせた、実践的な黒カビの落とし方をご紹介しますね。
4.1 お風呂(浴室)の黒カビの落とし方
お風呂は、黒カビが最も発生しやすい場所のひとつ。高い湿度、温かい温度、そして石鹸カスや皮脂といった栄養分。カビにとっては、まさに天国のような環境なのです。場所ごとに手ごわさも違うので、それぞれに合った方法で退治していきましょう。

4.1.1 ゴムパッキンやタイルの目地の頑固な黒カビ
ドアのゴムパッキンやタイルの目地に深く根を張った黒カビは、見た目も気になりますし、なかなか手ごわい相手です。洗剤が流れやすい垂直な場所なので、ひと工夫が必要になりますよ。
ここでおすすめなのが、塩素系漂白剤を使った「パック法」です。洗剤をカビにしっかりと密着させて、じっくりと成分を浸透させることができます。
- まず、カビの周りの水分をタオルなどでしっかりと拭き取ります。濡れていると洗剤が薄まって効果が弱まってしまうからです。
- 黒カビが気になる部分に、カビキラーなどの塩素系漂白剤をスプレーします。
- その上からキッチンペーパーを貼り付け、さらに洗剤をスプレーして湿らせます。
- 乾燥を防ぐために、キッチンペーパーの上からラップで覆い、15分から30分ほど放置します。
- 時間が経ったらラップとキッチンペーパーを剥がし、シャワーの水で洗剤をしっかりと洗い流しましょう。
最近では、垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤(「カビハイター ゴムパッキン用」など)も市販されています。こういった便利なアイテムを活用するのも良いですね。
4.1.2 天井や壁に広がった黒カビ
お風呂の天井や壁の黒カビは、胞子を浴室全体にまき散らす原因にもなります。お掃除の際は、洗剤が垂れて目や口に入らないように、細心の注意を払いましょう。ゴーグル、マスク、ゴム手袋は必ず着用してくださいね。

天井のお掃除で、洗剤を直接スプレーするのは絶対にやめましょう。液が垂れてきて大変危険です。柄の長いフロアワイパーにキッチンペーパーや乾いた布を取り付け、そこに洗剤を染み込ませてから、優しく天井に塗り広げるように掃除するのが安全です。
- 窓を開けたり換気扇を回したりして、しっかりと換気を行います。
- フロアワイパーにキッチンペーパーなどをセットし、塩素系漂白剤をスプレーして湿らせます。
- ワイパーを使い、天井や壁のカビに洗剤を優しく押し当てるように塗布します。ゴシゴシこする必要はありません。
- 製品に記載されている時間、放置します。
- その後、きれいな水で濡らして固く絞った布で洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で水分を拭き取って仕上げます。
4.1.3 床や排水溝の黒カビ
床や排水溝は、石鹸カスや皮脂汚れが溜まりやすく、黒カビの温床となりがちです。床の黒カビには、塩素系漂白剤をスプレーし、少し時間をおいてからブラシで軽くこすり、シャワーで洗い流しましょう。
排水溝は、蓋やヘアキャッチャーなどの部品を取り外し、それぞれに塩素系漂白剤をスプレーしてブラシでこすります。髪の毛やゴミを取り除いた後、パイプユニッシュのようなパイプクリーナーを使うと、奥の見えない部分のカビやぬめりもすっきりしますよ。
4.2 部屋の壁紙(クロス)に生えた黒カビの落とし方
お部屋の壁紙に黒カビを見つけると、気分も沈んでしまいますよね。壁紙はデリケートな素材なので、お風呂場と同じようにお掃除すると傷めてしまう可能性があります。素材を確認してから、慎重に進めましょう。
4.2.1 ビニールクロスの黒カビ掃除法
日本の住宅で最も多く使われているのが、ビニールクロスです。表面がビニール素材でコーティングされているため、比較的お掃除がしやすいのが特徴です。見分け方は、霧吹きなどで少しだけ水をかけてみること。水を弾けばビニールクロスの可能性が高いです。
ビニールクロスの黒カビには、消毒用エタノールがおすすめです。塩素系漂白剤は壁紙を変色させてしまう恐れがあるため、使う場合は必ず目立たない場所で試してからにしてくださいね。
- まず、乾いた布やブラシで壁紙のホコリを優しく払い落とします。
- 消毒用エタノールをきれいな布に染み込ませます。
- カビの部分を、ゴシゴシこするのではなく、ポンポンと優しく叩くように拭き取ります。こするとカビが広がったり、壁紙を傷めたりする原因になります。
- カビが取れたら、水で濡らして固く絞った布でエタノールを拭き取り、最後に乾拭きで仕上げます。
4.2.2 賃貸物件で試す前に確認すべきこと
もしお住まいが賃貸物件の場合は、ご自身で対処する前に一度立ち止まりましょう。賃貸物件には「原状回復義務」があり、万が一お掃除で壁紙を傷めたり変色させたりしてしまうと、退去時に修繕費用を請求されることがあります。まずは大家さんや管理会社に状況を報告し、どのように対処すべきか相談するのが一番安心な方法です。
4.3 エアコンから出る黒カビの掃除方法
夏や冬に大活躍のエアコンですが、その内部は結露によって湿気が溜まりやすく、ホコリを栄養にして黒カビが繁殖しやすい場所です。エアコンの風に乗ってカビの胞子が部屋中に広がるのは、健康のためにも避けたいですよね。

4.3.1 自分でできるフィルターと吹き出し口の掃除
ご家庭で安全にお掃除できるのは、「フィルター」と「吹き出し口(風が出てくる部分)」までです。お掃除の前には、感電や故障を防ぐため、必ずエアコンの電源プラグを抜いてくださいね。
- フィルター:取り外して、まずは掃除機で表面のホコリを吸い取ります。その後、シャワーなどで水洗いし、汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤と柔らかいブラシで優しく洗いましょう。洗い終わったら、風通しの良い日陰で完全に乾かしてから元に戻します。
- 吹き出し口:割り箸にキッチンペーパーを巻き付けた手作りのお掃除棒などに、消毒用エタノールを少量染み込ませます。それで、吹き出し口の羽根(ルーバー)や内部の見える範囲を優しく拭き取っていきます。
4.3.2 エアコン内部の黒カビは専門業者への依頼がおすすめ
フィルターの奥にある冷却フィンや送風ファンといったエアコン内部は、構造が複雑で電装部品もあるため、ご自身で分解して掃除するのは大変危険です。市販のエアコン洗浄スプレーもありますが、洗い流しが不十分だと内部で汚れが固まってしまったり、故障や火災の原因になったりするリスクも指摘されています。
エアコン内部の本格的なお掃除は、1〜2年に一度を目安に、プロのハウスクリーニング業者に依頼するのが最も安全で確実な方法です。
4.4 窓のサッシやゴムパッキンの黒カビの落とし方
冬場の結露によって、窓のサッシやゴムパッキンは常に湿った状態になりがち。ホコリも溜まりやすく、気づいたときには黒カビがびっしり…なんてことも。ここも、お風呂のゴムパッキン掃除でご紹介した塩素系漂白剤のパック法が有効です。
細かい部分が多いので、使い古しの歯ブラシや綿棒が大活躍します。洗剤を塗布したあと、しばらく放置して水拭きと乾拭きで仕上げましょう。塩素の臭いが気になる方は、重曹とクエン酸を使ったナチュラルな方法も試せます。重曹を水で練ってペースト状にしたものをカビに塗り、その上からクエン酸水をスプレーするとシュワシュワと発泡し、カビを浮かせてくれますよ。
4.5 キッチンのシンク周りやコーキングの黒カビ
キッチンも、水を使うためカビが発生しやすい場所です。特に、シンクと壁のつなぎ目にあるゴムの部分(コーキング)は、水垢や食材のカスが溜まりやすく、黒カビの温床になります。
ここでも活躍するのは、キッチンハイターなどの塩素系漂白剤です。お風呂のパッキン掃除と同じ要領で、キッチンペーパーを使ったパック法を試してみてください。食品を扱う場所ですので、お掃除の後は、洗剤の成分が残らないように、何度も水拭きを繰り返して念入りに仕上げましょう。
4.6 洗濯槽の見えない黒カビの落とし方
洗いたての洗濯物に、黒いワカメのようなカスが付いていたことはありませんか?その正体は、洗濯槽の裏側にびっしりと繁殖した黒カビです。見えない場所だからこそ、定期的にお手入れして清潔に保ちたいですよね。
お掃除には、市販の洗濯槽クリーナーを使いましょう。クリーナーには主に「酸素系」と「塩素系」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 酸素系(粉末) | 発泡する力でカビを剥がし取る | 汚れが目に見えて取れるので、すっきり感が強い。環境にやさしい。 | つけ置きに時間がかかる。剥がれたカビをすくい取る手間がある。 |
| 塩素系(液体) | 強力な殺菌力でカビを分解して溶かす | つけ置き不要で短時間で終わる。手間がかからない。 | ツンとした特有の臭いがある。「混ぜるな危険」の表示があり、取り扱いに注意が必要。 |
酸素系クリーナー(オキシクリーンなど)を使う場合は、40〜50℃のお湯を使うと効果がぐっと高まります。洗濯槽にお湯をためてクリーナーを溶かし、数時間つけ置きしたあと、浮いてきた汚れを網ですくい取り、標準コースで運転すれば完了です。月に1回程度の定期的なお掃除で、毎日のお洗濯を気持ちよく行いましょう。
5. 自分では落とせない色素沈着した黒カビの対処法
いろいろな洗剤を試して、時間をかけてお掃除をしても、どうしても黒いシミが残ってしまうことがありますよね。一生懸命がんばった後だと、余計にがっかりしてしまうものです。でも、それはあなたの掃除方法が間違っているわけではないのかもしれません。ここでは、そんな頑固な黒カビの正体と、プロの力を借りるという選択肢について、丁寧にご紹介しますね。
5.1 洗剤でも落ちない黒カビの正体
カビ取り剤を使っても消えない黒いシミの正体、それはカビが作り出した色素が、素材の奥深くに染み込んでしまった「色素沈着」です。お洋服に付いたインクのシミが、洗濯してもなかなか落ちないのと似ていますね。
特に、お風呂のゴムパッキンやキッチンのコーキング(シリコン)部分は、柔らかい素材でできているため、色素が内部まで浸透しやすいのです。カビそのものはすでに死滅していて、健康への影響は少なくなっている場合がほとんどですが、見た目だけが黒く残ってしまいます。これは汚れというよりも「シミ」に近い状態なので、表面をきれいにする洗剤だけでは落とすのがとても難しいのです。
5.2 ハウスクリーニング業者に依頼するメリットと費用相場
ご自身での対処が難しいと感じたら、無理せずお掃除のプロであるハウスクリーニング業者さんにお願いするのも、暮らしを快適にするための賢い選択肢のひとつですよ。時間や手間を省けるだけでなく、専門家ならではの知識と技術で、見違えるほどきれいにしてくれることもあります。
プロに依頼する主なメリットは、次の通りです。
- 専門の薬剤や機材で対応してくれる:市販されていない強力な薬剤や、素材を傷めにくい特別な道具を使って、色素沈着を薄くしてくれる場合があります。
- 時間と労力が節約できる:面倒で時間のかかるカビ取り作業から解放され、ご自身の趣味や休息の時間をゆっくりと楽しめます。
- 自分では難しい場所も徹底的に:浴室の天井やエプロン内部、エアコンの奥など、普段なかなか手の届かない場所も隅々まで掃除してもらえます。
- 再発防止のアドバイスがもらえることも:お家の状況に合わせたカビ予防の方法など、プロならではの視点で的確な助言をくれることもあります。
気になる費用ですが、場所や汚れの範囲によって変わってきます。一般的な相場をまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね。
| 掃除を依頼する場所 | 費用相場 | 作業時間の目安 |
|---|---|---|
| 浴室(お風呂)全体 | 15,000円~30,000円 | 2~4時間 |
| エアコン(壁掛けタイプ) | 10,000円~20,000円 | 1.5~3時間 |
| キッチン全体 | 18,000円~35,000円 | 3~5時間 |
※費用や時間は、汚れの状態や業者さんによって変わりますので、あくまで目安としてお考えくださいね。
業者さんを選ぶ際は、複数の会社から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討することをおすすめします。その際、どこまでの作業が含まれているのか、追加料金が発生する可能性はあるのかを事前にしっかり確認しておくと、後々のトラブルを防ぐことができ安心です。最近はインターネットで口コミなども手軽に調べられますので、そういった情報も参考にしながら、ご自身に合った信頼できる業者さんを見つけてくださいね。
6. もう発生させない 黒カビの徹底的な予防方法
大変な黒カビ掃除、もう繰り返したくはないですよね。せっかくきれいにしたのですから、これからはカビが生えにくい心地よいお家を保ちましょう。カビは「温度」「湿度」「栄養」の3つの条件がそろうと発生します。この3つのうち、どれか一つでも断ち切ることが、カビ予防のいちばんの近道なんですよ。ここでは、毎日の暮らしの中で手軽にできる、黒カビの徹底的な予防方法をご紹介します。
6.1 基本は換気 湿度をコントロールする
カビ対策の基本は、なんといっても「換気」です。お部屋の空気を入れ替えて、カビが大好きでたまらない湿気を外に追い出してしまいましょう。カビが活発になるのは湿度が60%以上の環境だといわれています。上手な換気で、お家の中をカビが住みにくい環境に変えていきましょう。
換気の方法は、決して難しくありません。2か所以上の窓を5分から10分ほど開けて、空気の通り道を作ってあげるだけで十分です。お部屋の対角線上にある窓を開けると、空気が効率よく流れてくれますよ。雨の日は窓を開けると逆に湿気が入ってきてしまうので、エアコンの「除湿(ドライ)」機能を使うのがおすすめです。
また、最近の住宅についている「24時間換気システム」は、基本的に止めずに使い続けるのが正解です。お風呂やキッチンの換気扇も、使った後しばらく回しておく習慣をつけると、湿気がこもりにくくなります。クローゼットや押し入れなど、空気がよどみがちな場所には、サーキュレーターで風を送ってあげるのも良い方法です。
6.2 お風呂上がりの一手間でカビ予防
家の中で最もカビが発生しやすいお風呂場。でも、毎日のお風呂上がりにほんの少し手間をかけるだけで、カビの発生をぐっと抑えることができるんです。面倒に感じるかもしれませんが、慣れてしまえば簡単な気持ちのいい習慣になりますよ。
カビ予防のポイントは、カビの「栄養」となる石鹸カスや皮脂汚れを洗い流し、「温度」と「湿度」を素早く下げること。具体的なステップを下の表にまとめました。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 熱いシャワーで流す | お風呂から出る前に、壁や床全体を熱いシャワーで洗い流します。 | 50℃以上のお湯を5秒以上かけると、カビの殺菌効果が期待できます。石鹸カスなどの汚れも一緒に流せます。 |
| 2. 冷たいシャワーで冷やす | 次に、冷たいシャワーで浴室全体の温度を下げます。 | 湯気を一気に抑え、浴室の温度を下げることで結露を防ぎます。 |
| 3. 水気を拭き取る | スクイージー(水切りワイパー)や乾いたタオルで、壁や床、鏡の水滴を取り除きます。 | カビの発生原因となる水分を物理的に取り除く、最も効果的な方法です。 |
| 4. 換気扇を回す | 浴室のドアを少し開けた状態で、換気扇を回します。 | 最低でも2〜3時間は回し続けましょう。朝までつけっぱなしにしておくと、さらに効果的です。 |
6.3 結露対策で窓や壁のカビを防ぐ
冬になると悩まされるのが、窓ガラスにびっしりとつく「結露」です。見た目も気になりますが、実はこの結露が窓のサッシやゴムパッキン、カーテン、さらには壁紙の黒カビの大きな原因になっているのです。
結露は、室内の暖かい空気が冷たい窓に触れることで発生します。この水分を放っておくと、ホコリなどと結びついてカビの温床になってしまいます。結露を見つけたら、吸水性の高い布や結露取りワイパーでこまめに拭き取る習慣をつけましょう。
毎回拭くのが大変…という方は、予防策を取り入れるのがおすすめです。窓に市販の「断熱シート」を貼ったり、カーテンを厚手のものに変えたりするだけでも、外の冷気が伝わりにくくなり、結露を軽減できます。また、壁と家具の間を5cmほどあけて置くようにすると、空気の通り道ができて壁のカビ予防につながりますよ。
6.4 市販の防カビ剤を効果的に活用する
日々の予防習慣に加えて、便利な市販の防カビ剤を取り入れると、さらにカビ対策が楽になります。お掃除の仕上げとして、上手に活用してみましょう。
代表的なのは、お風呂場で使う「防カビくん煙剤」です。煙の力で有効成分が浴室の隅々まで行き渡り、黒カビの原因菌をまるごと除菌して、カビが生えにくい状態を保ってくれます。製品によって異なりますが、1〜2ヶ月に一度、定期的に使うのがおすすめです。
そのほかにも、壁やクローゼットに直接使えるスプレータイプや、下駄箱やシンク下に置くタイプなど、用途に合わせて様々な商品があります。ご家庭の気になる場所に合わせて選んでみてくださいね。
防カビ剤を使う上でとても大切なポイントが一つあります。それは、必ずカビをきれいに掃除してから使用することです。すでに生えているカビの上から使っても、十分な効果は得られません。きれいな状態をキープするための「お守り」として、ぜひ活用してみてください。
7. まとめ
この記事では、お家の気になる黒カビの原因から、お風呂や壁など場所別の掃除方法、そして大切な予防法までご紹介しました。黒カビはアレルギーの原因にもなるため、見つけたら早めの対処が肝心です。カビキラーなど適切な洗剤を正しく使えば、諦めていた頑固な汚れもきれいに落とせます。そして何より大切なのは、日々の予防。こまめな換気や水気を拭き取る習慣で、カビの発生しにくい心地よい空間を保ちましょう。この記事が、あなたらしく快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。

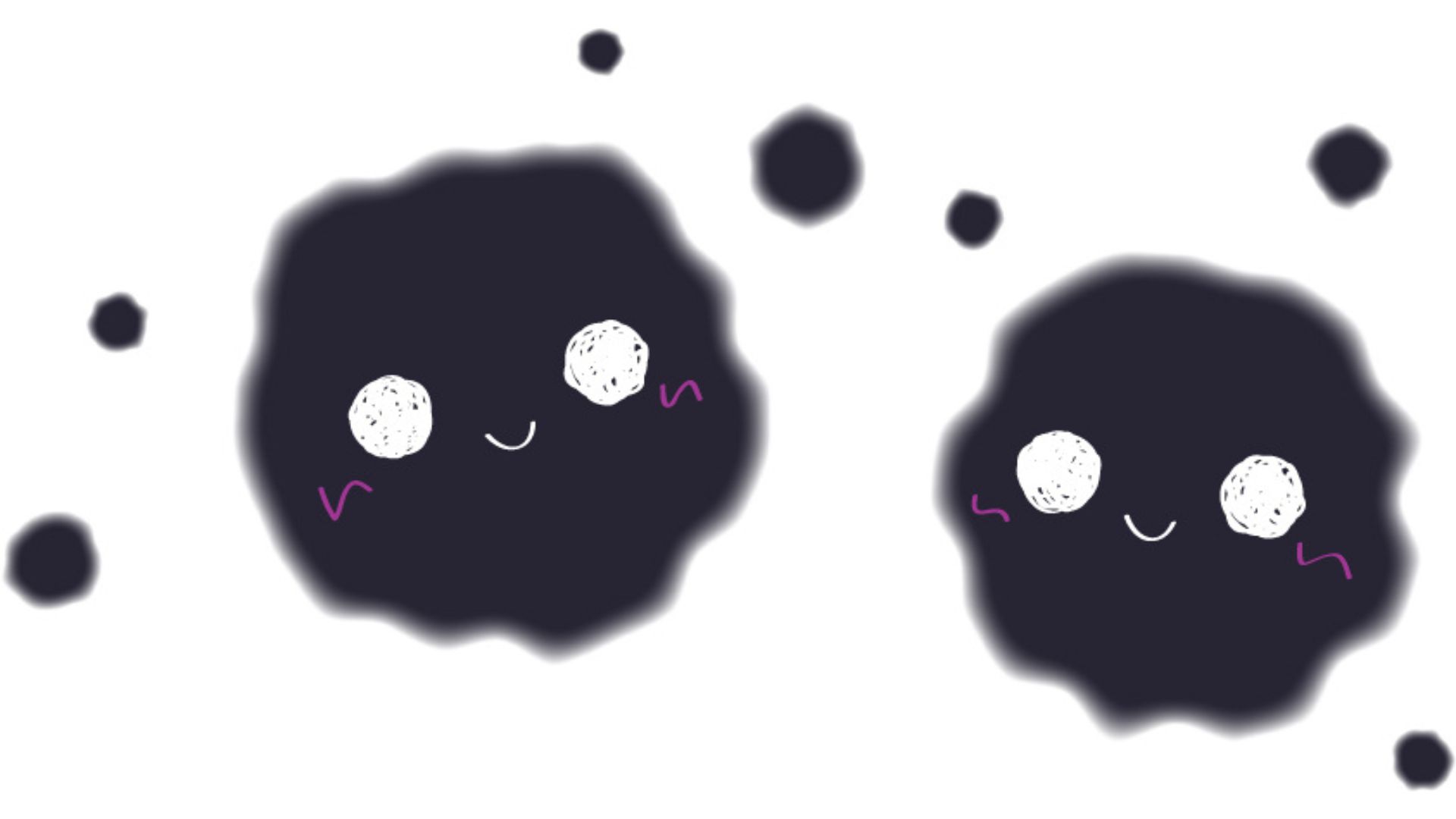








コメント