寒中見舞いは、松の内が明けてから立春までに出す、冬の季節のご挨拶です。年賀状の代わりや喪中のご挨拶にもなり、暮らしのなかで役立つ習慣ですが、いざ書こうとすると時期や書き方に迷うことも。この記事では、寒中見舞いの基本マナーから、相手や状況に応じた例文、ふとした疑問まで丁寧に解説します。心のこもった一通で、大切な方へあたたかな気持ちを届けてみませんか。

1. 寒中見舞いとは?年賀状との違いも解説
一年で最も寒さが厳しい季節に、相手の健康を気遣い、お互いの近況を伝えあう心温まる習慣、それが「寒中見舞い」です。なんだか少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、大切なのは相手を思いやる気持ち。暮らしのひとコマに、季節の便りを取り入れてみませんか。

寒中見舞いは、寒さが厳しい時期に送る季節の挨拶状のこと。お世話になっている方やご無沙汰している方へ「寒い日が続きますが、お元気にされていますか?」と安否を気遣うために送ります。また、年賀状の代わりや、いただいた年賀状への返礼としても使うことができる、とても便利な挨拶状なんですよ。
では、お正月の挨拶状である「年賀状」とは、具体的に何が違うのでしょうか。一番の違いは、その目的と送る時期にあります。それぞれの役割を知ると、いざという時に迷わず使い分けることができますよ。
| 項目 | 寒中見舞い | 年賀状 |
|---|---|---|
| 目的 | 厳しい寒さの中、相手の健康を気遣う季節の挨拶 | 新しい年を迎えたお祝いと、旧年中の感謝を伝える新年の挨拶 |
| 出す時期 | 松の内が明けてから立春まで | 元日(1月1日)から松の内(1月7日頃)まで |
| 主な用途 | 季節の挨拶 喪中の相手への挨拶 自分や相手が喪中で年賀状が出せなかった場合の挨拶 年賀状の返事が遅れた場合のお詫びと挨拶 | 新年の挨拶 日頃お世話になっている方への感謝 近況報告 |
| 挨拶の言葉 | 「寒中お見舞い申し上げます」 | 「明けましておめでとうございます」などのお祝いの言葉(賀詞) |
このように、年賀状が「おめでとう」というお祝いの気持ちを伝えるのに対し、寒中見舞いは「お元気ですか」と相手を気遣う見舞い状としての性格が強いのが特徴です。そのため、喪中のように年賀状を控えなければならない場合にも、季節の挨拶状として送ることができます。

2. 寒中見舞いを出す時期はいつからいつまで?
季節の挨拶状である寒中見舞い。いざ送ろうと思ったときに「いつからいつまでに出せばいいのかしら?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。寒中見舞いは、送る時期がとても大切です。早すぎても遅すぎても、お相手に失礼にあたってしまう可能性があります。ここでは、寒中見舞いを出すのにふさわしい時期について、詳しく見ていきましょう。
2.1 寒中見舞いは松の内が明けてから立春まで
寒中見舞いを出す期間は、一般的に「松の内(まつのうち)」が明けてから、「立春(りっしゅん)」の前日までとされています。
「松の内」とは、お正月に門松やしめ縄といった松飾りを飾っておく期間のこと。この期間はまだ新年のご挨拶である年賀状をやりとりする時期にあたります。そのため、松の内が明けて、お正月の雰囲気が落ち着いた頃から寒中見舞いを出し始めるのがマナーです。
そして、「立春」は暦の上で春が始まる日。立春を過ぎると「寒中」ではなくなるため、寒中見舞いは立春の前日までに届くように送りましょう。寒い時期に相手の健康を気遣う、心温まるお便りです。ふさわしい時期に届けることで、その気持ちがより一層伝わりますね。
2.2 【2025年版】松の内はいつまで?関東と関西で異なる時期
実は、「松の内」の期間は地域によって違いがあることをご存知でしたか?主に関東と関西で期間が異なるため、ご自身がお住まいの地域やお相手の地域に合わせて時期を調整すると、より丁寧な印象になります。
2025年の具体的な日付で確認してみましょう。2025年の立春は2月4日(火)ですので、この日より前に届くように出すのが目安です。
| 地域 | 松の内の期間 | 寒中見舞いを出す時期(2025年) |
|---|---|---|
| 関東地方 | 1月1日~1月7日 | 1月8日(水)~2月3日(月)頃 |
| 関西・東海・中国・四国・九州地方など | 1月1日~1月15日 | 1月16日(木)~2月3日(月)頃 |
このように、関東では1月7日までが松の内とされるため、1月8日から寒中見舞いの期間となります。一方、関西やその他の多くの地域では1月15日までが松の内ですので、1月16日から出し始めるのが一般的です。どちらの地域に合わせるか迷った場合は、1月15日を過ぎてから送るようにすれば、どの地域の方に対しても失礼にあたることはないでしょう。
(暦の情報は、国立天文台 暦計算室の情報を参考にしています。)
2.3 立春を過ぎてしまったら余寒見舞いを出す
「うっかり準備が遅れて、立春を過ぎてしまった…」そんな時でも、どうぞご安心ください。立春を過ぎてしまった場合には、「余寒見舞い(よかんみまい)」としてお便りを出すことができます。
余寒見舞いは、立春(2025年は2月4日)から2月末ごろまでに出すのが目安です。「暦の上では春になりましたが、まだ寒い日が続いておりますので、どうぞご自愛ください」といったように、残る寒さを気遣う内容で送ります。
挨拶状の書き出しも「寒中お見舞い申し上げます」から「余寒お見舞い申し上げます」に変えるだけで、内容は寒中見舞いと同じように使えます。時期を逃してしまったからと諦めずに、季節の挨拶状を送ってみてはいかがでしょうか。きっとお相手にも喜ばれるはずです。

3. 寒中見舞いの基本的な書き方と構成
寒中見舞いは、相手を気遣う心を伝える大切な季節の挨拶状です。いざ書こうとすると、何から書き始めればよいか迷ってしまうこともありますよね。でも、心配はいりません。基本的な構成さえ押さえておけば、誰でも心のこもった寒中見舞いを書くことができますよ。ここでは、基本的な書き方の手順から、はがきや切手の選び方、知っておきたいマナーまで、一つひとつ丁寧にご紹介します。
3.1 寒中見舞いを書く際の5つのステップ
寒中見舞いは、決まった構成に沿って書くと、まとまりやすく、気持ちも伝わりやすくなります。以下の5つのステップを参考に、あなたらしい言葉を紡いでみましょう。
| ステップ | 内容 | 書き方のポイントと例文 |
|---|---|---|
| 1. 時候の挨拶 | 「寒中お見舞い申し上げます」という決まり文句です。 | はがきの最初に、少し大きめの文字で書きます。これが表題の役割を果たします。 例文:「寒中お見舞い申し上げます」 |
| 2. 相手の安否を気遣う言葉 | 時候の挨拶に続けて、相手の健康や様子を気遣う言葉を書きます。 | 厳しい寒さの中、相手が元気に過ごしているかを尋ねる、思いやりの言葉を添えましょう。 例文:「厳しい寒さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」 「例年にない寒さですが、皆様お元気でいらっしゃいますか。」 |
| 3. 自分の近況報告 | 自分のことや家族の様子を簡潔に伝えます。 | 長々と書く必要はありません。「おかげさまで私どもは元気に暮らしております」といった一言で十分です。趣味のことなど、ひと言添えるのも素敵ですね。 例文:「おかげさまで、私どもは変わりなく元気に過ごしております。」 「寒さに負けず、庭の椿が美しい花を咲かせております。」 |
| 4. 相手の健康を願う言葉 | 文章の結びとして、相手の無事や健康を祈る言葉で締めくくります。 | これからも続く寒さに、相手が体調を崩さないように気遣う言葉を選びましょう。 例文:「寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください。」 「皆様の無病息災を心よりお祈り申し上げます。」 |
| 5. 日付 | はがきを書いた日付を入れます。 | 「令和七年 一月」のように、年と月までを書き、具体的な日付は書かないのが一般的です。「一月」の代わりに、二十四節気の「大寒」などと記すのも趣があります。 例文:「令和七年 一月」 |
3.2 使用するはがきや切手のマナー
寒中見舞いを送る際には、はがきや切手の選び方にも少しだけ心配りをしたいもの。相手に失礼のないよう、基本的なマナーを知っておくと安心です。
3.2.1 年賀はがきは使ってもいい?
余った年賀はがきを寒中見舞いに使うのは、基本的には避けましょう。年賀はがきは、新年を祝う「賀」の文字が入っているため、松の内が明けてからの挨拶状にはふさわしくないとされています。特に、喪中の方への挨拶として送る場合は、絶対に使用してはいけません。
もし、どうしても手元に年賀はがきしかなく、やむを得ず使用する場合は、料額印面(切手部分)の下にある「年賀」の文字を二重線でしっかりと消してから投函します。しかし、これはあくまで緊急の対応策。相手に丁寧な印象を与えるためにも、できるだけ通常の郵便はがきや、季節の花などが描かれた私製はがきを使うことをおすすめします。
3.2.2 切手は通常のもので問題ない
寒中見舞いに貼る切手は、通常の普通切手でまったく問題ありません。お祝い用の「慶事用切手」は、おめでたい場面で使うものなので、寒中見舞いには不向きです。特に、喪中の方へ送る際には、華やかなデザインの切手は避けるのがマナーです。
もし少しこだわりたいなら、季節感のあるデザインの切手を選ぶと、受け取った方も心が和むでしょう。日本郵便では、冬の花や風景をあしらった素敵なグリーティング切手が発行されています。郵便局の窓口で相談したり、公式サイトで探してみたりするのも楽しいですよ。
3.3 寒中見舞いにおける書き方の注意点
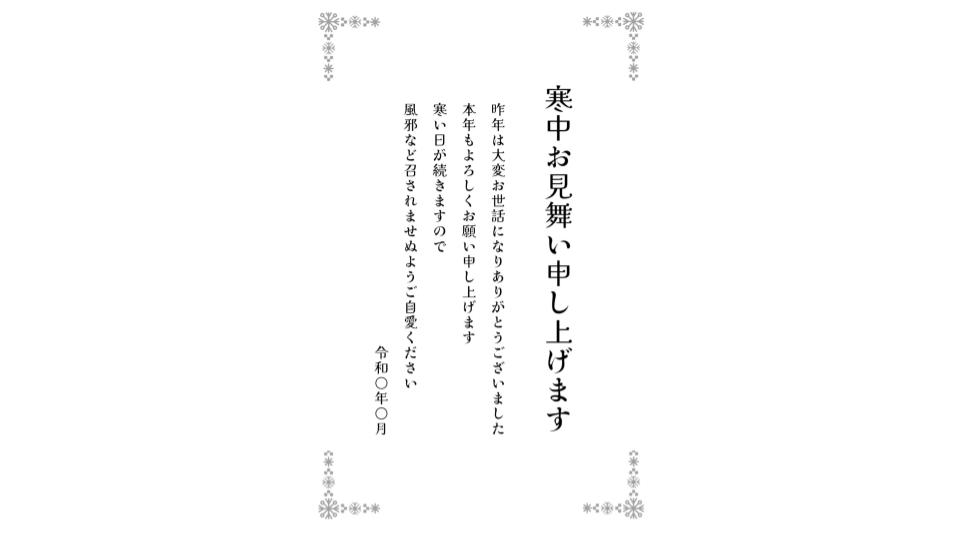
最後に、寒中見舞いを書く上で気をつけたい細かな注意点をご紹介します。知っておくと、より洗練された印象の挨拶状になりますよ。
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| 句読点は使わないのが伝統 | 伝統的な書式では、「、」や「。」といった句読点は用いません。これは「縁が切れないように」「お祝い事が途切れないように」という願いが込められているためです。 |
| 頭語・結語は不要 | 「拝啓」「敬具」のような頭語・結語は、寒中見舞いには必要ありません。「寒中お見舞い申し上げます」の挨拶から書き始めましょう。 |
| 「賀」などおめでたい言葉は避ける | 寒中見舞いは年賀状ではないため、「賀正」「迎春」「おめでとう」といったお祝いの言葉(賀詞)は使いません。特に、年賀状の返信が遅れた場合や、喪中の相手に送る際には細心の注意が必要です。 |
| 近況報告の内容に配慮する | 結婚や出産といった喜ばしい報告は、相手が喪中でないことを確認してからにしましょう。相手が喪中の場合は、おめでたい話題には触れず、静かに寄り添う言葉を選ぶのが思いやりです。 |
ただし、句読点については、現代では読みやすさを優先して使っても失礼にはあたらない、という考え方が一般的になっています。相手との関係性に合わせて、使い分けるとよいでしょう。大切なのは、形式よりも相手を気遣う心です。これらのポイントを参考に、あなたらしい温かな寒中見舞いを届けてみてくださいね。
4. 【相手・状況別】そのまま使える寒中見舞いの例文集
寒中見舞いは、送るお相手やご自身の状況によって、少しずつ言葉を選ぶ必要があります。ここでは、様々な場面でそのままお使いいただける例文をいくつかご用意いたしました。あなたらしい言葉を添える際の、ヒントにしていただけたら嬉しいです。
4.1 一般的な季節の挨拶として送る場合の例文
親しいご友人や知人、お世話になっている方へ、純粋な季節のご挨拶として送る場合の例文です。厳しい寒さが続く中、相手の健康を気遣うあたたかな一言を添えましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 主な内容 | 時候の挨拶、相手の健康を気遣う言葉、ご自身の近況、結びの挨拶 |
| ポイント | 堅苦しくなりすぎず、心温まるような言葉を選びましょう。近況報告は、受け取った相手がほっとするような、ささやかな話題がおすすめです。 |
【例文】
寒中お見舞い申し上げます
厳しい寒さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
こちらは、庭の梅のつぼみも少しずつ膨らみはじめ、春の訪れが待ち遠しい毎日です。
まだまだ寒い日が続きますので、どうぞ暖かくしてご自愛くださいね。
またお会いできる日を楽しみにしております。
令和七年一月
4.2 年賀状のお礼や返事が遅れた場合の例文
年賀状をいただいたものの、返信が松の内を過ぎてしまった場合に用いる例文です。お正月の挨拶をいただいたことへのお礼と、返事が遅れたことへのお詫びを丁寧に伝えましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 主な内容 | 時候の挨拶、年賀状へのお礼、返信が遅れたお詫び、相手の健康を気遣う言葉、結びの挨拶 |
| ポイント | まずはじめに、素敵な年賀状をいただいたことへの感謝を伝えます。その上で、ご挨拶が遅れてしまったことを丁寧にお詫びするのがマナーです。 |
【例文】
寒中お見舞い申し上げます
この度は、ご丁寧な年始のご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。
ご挨拶が遅れまして、大変失礼いたしました。
皆様おそろいで、健やかな新年をお迎えになられたご様子、心よりお慶び申し上げます。
私どもも変わりなく過ごしておりますので、ご安心ください。
寒さ厳しき折、皆様のますますのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
令和七年一月
4.3 喪中の相手へ寒中見舞いを送る場合の例文
年賀状を出すのを控えた、喪中の方へご挨拶状を送る際の例文です。お悔やみの言葉や、相手の心を気遣う言葉を添えて、静かにお見舞いの気持ちを伝えましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 主な内容 | 時候の挨拶、相手を気遣う言葉、お悔やみの言葉、励ましの言葉、結びの挨拶 |
| 注意点 | お祝いの言葉である「賀」の字や、「おめでとうございます」といった言葉は使いません。「年始のご挨拶は遠慮させていただきましたが」と一言添えることで、相手への配慮が伝わります。故人のことに触れる場合は、あまり立ち入りすぎず、相手の気持ちに寄り添うことを心がけましょう。 |
【例文】
寒中お見舞い申し上げます
ご服喪中のことと存じ、年始のご挨拶は遠慮させていただきました。
ご家族の皆様には、さぞご寂しい思いでお過ごしのこととお察しいたします。
寒さ厳しき折、くれぐれもご無理なさらないでくださいね。
心ばかりの品をお送りいたしましたので、どうぞお納めください。
皆様が一日も早く、心穏やかな日々を取り戻されますよう、心よりお祈り申し上げます。
令和七年一月
4.4 自分が喪中で年賀状の返礼として送る場合の例文
ご自身が喪中のときに年賀状をいただいた場合、その返礼として寒中見舞いを送ります。喪中であったために年賀状でのご挨拶ができなかった旨を伝え、相手の健康を気遣う言葉を添えましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 主な内容 | 年賀状へのお礼、喪中であったため年始の挨拶を控えた旨、相手の健康を気遣う言葉、結びの挨拶 |
| ポイント | 年賀状をいただいたことへの感謝を述べた上で、「昨年(続柄)が永眠いたしましたため、年末年始のご挨拶を控えさせていただきました」と、喪中であったことを伝えます。誰がいつ亡くなったかを簡潔に記すと、より丁寧です。詳しくは日本郵便のウェブサイトも参考になります。 |
【例文】
寒中お見舞い申し上げます
ご丁寧な年始のご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。
昨年十一月に父が永眠いたしましたため、年末年始のご挨拶を控えさせていただきました。
ご連絡が遅くなり、大変申し訳ございません。
寒さ厳しき折、皆様どうぞご自愛の上お過ごしください。
本年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和七年一月
4.5 ビジネスで上司や取引先に送る場合の例文
上司や取引先など、お仕事でお世話になっている方へ送る寒中見舞いの例文です。丁寧な言葉遣いを心がけ、日頃の感謝の気持ちと、今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉を添えましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 主な内容 | 時候の挨拶、日頃の感謝、相手の会社の繁栄を願う言葉、結びの挨拶 |
| ポイント | プライベートな内容には深入りせず、あくまでもビジネス上のご挨拶として簡潔にまとめます。「平素は格別のご高配を賜り」といった、ビジネスシーンにふさわしい言葉を選びましょう。 |
【例文】
寒中お見舞い申し上げます
寒さ厳しき折、〇〇様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
まだまだ寒さが続きますが、くれぐれもご自愛ください。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和七年一月
5. 寒中見舞いにまつわるQ&A
いざ寒中見舞いを用意しようとすると、ふと「こんなとき、どうしたらいいのかしら?」と迷うこともありますよね。ここでは、寒中見舞いにまつわる細やかな疑問にお答えします。一つひとつ確認して、心からのご挨拶を届けましょう。
5.1 寒中見舞いをもらったら返事は必要?
寒中見舞いをいただいたとき、お返事をすべきか悩む方もいらっしゃるかもしれませんね。結論から言うと、必ずしもお返事は必須ではありませんが、お返事を出すとより丁寧な印象になります。
寒中見舞いは、寒い季節に相手の健康を気遣うお便りです。その温かいお心遣いに対して、こちらからも感謝の気持ちと相手を気遣う言葉をお返しするのは、とても素敵な心遣いと言えるでしょう。
もしお返事を出す場合は、立春(2月4日頃)までに相手に届くように送りましょう。万が一、立春を過ぎてしまった場合は「余寒見舞い」としてお返事を出すと良いですよ。その際は、「暦の上では春となりましたが、まだ寒い日が続きますね」といった一文を添えると、季節感も伝わります。
5.2 メールやLINEで寒中見舞いを送るのは失礼?
最近では、メールやLINEで手軽に挨拶を交わすことも増えましたね。寒中見舞いをデジタルで送ることが失礼にあたるかどうかは、お相手との関係性によって使い分けるのがおすすめです。
親しいご友人や気心の知れた間柄であれば、メールやLINEでのご挨拶もまったく問題ありません。一方で、お仕事でお世話になっている上司や取引先の方、恩師など、目上の方へは、やはり伝統的なはがきで送るのが最も丁寧で、礼儀にかなっています。
特に、喪中の方へお悔やみの気持ちを込めて送る場合は、はがきの方がより一層、いたわりの心が伝わりやすいでしょう。状況に応じた使い分けを下の表にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
| 送る相手 | はがき | メール・LINE |
|---|---|---|
| 目上の方(上司・恩師など) | ◎(丁寧で安心です) | △(避けるのが無難です) |
| 親しい友人や同僚 | ○ | ○(手軽で気持ちが伝わります) |
| 親族 | ○ | ○(関係性によります) |
| 喪中の方 | ◎(心を込めて送るのにおすすめです) | △(はがきの方がより丁寧です) |
もしメールやLINEで送る場合は、「メール(LINE)にて失礼いたします」といった一言を添えると、より丁寧な印象になりますよ。
5.3 寒中見舞いにはがきに写真を使ってもいい?
寒中見舞いに写真を使うこと自体は、マナー違反ではありません。ただし、年賀状とは目的が異なるため、送る相手や状況への配慮が大切です。
ご自身の近況を伝えるために、穏やかな風景や可愛らしいペットの写真、趣味の作品などを添えるのは素敵ですね。親しいご友人やご親族であれば、きっと喜んでくださるでしょう。
ただし、注意したいケースが2つあります。
一つ目は、喪中の方へ送る場合です。お祝い事を連想させるような華やかな写真や、ご家族の笑顔があふれる写真は、相手のお気持ちを考えると避けるのが賢明です。冬景色や雪の結晶、静かなお花など、落ち着いたデザインのものを選びましょう。
二つ目は、ご自身が喪中の場合です。こちらも同様に、派手な印象を与える写真は控え、落ち着いたデザインを心がけましょう。
寒中見舞いは、あくまでも「寒い時期の健康を気遣うご挨拶状」です。その目的にふさわしい、穏やかで心温まるデザインを選ぶことが、相手への思いやりにつながります。
6. まとめ
今回は、寒中見舞いの時期やマナー、状況に応じた文例をご紹介しました。寒中見舞いは、一年で最も寒さが厳しい時期に、相手の健康を気遣う心温まる日本の風習です。松の内が明けてから立春までという短い期間に送るのがマナー。少し難しく感じるかもしれませんが、心を込めて綴ることで、きっと温かな気持ちが伝わるはずです。この記事を参考に、大切な方へ季節のご挨拶を送ってみてはいかがでしょうか。










コメント