大晦日の夜、どこからか聞こえてくる除夜の鐘の音。その意味や由来を、あなたはご存知でしょうか。この記事では、除夜の鐘がなぜ108回なのかという理由から、その歴史、鐘をつく時間や作法、参加できるお寺まで、気になる疑問をわかりやすく解説します。除夜の鐘は、一年間の煩悩を祓い、清らかな心で新年を迎えるための大切な儀式。その意味を知れば、今年の鐘の音はまた違った趣で心に響くかもしれません。


1. 除夜の鐘とは 大晦日に鳴り響く鐘の基本的な意味
大晦日の夜、しんしんと冷える空気のなか、どこからともなく聞こえてくる「ゴーン…」という厳かで心に響く鐘の音。この音を聞くと、「ああ、今年ももう終わりなのだな」と、一年を振り返る方も多いのではないでしょうか。この日本ならではの美しい年の瀬の風物詩が「除夜の鐘」です。

毎年当たり前のように耳にしている除夜の鐘ですが、その一つひとつの音には、私たちの心と暮らしに寄り添う、深く温かい意味が込められています。まずは、その基本的な意味から、一緒に紐解いていきましょう。
1.1 「除夜」という言葉に込められた特別な意味
そもそも「除夜(じょや)」とは、どのような意味を持つ言葉なのでしょうか。「除夜」とは、「古い年を除き、新しい年を迎える夜」、つまり大晦日の夜のことを指す言葉です。
漢字を一つずつ見てみると、その意味がより分かりやすくなりますよ。
| 漢字 | 意味 |
|---|---|
| 除 | 古いものを払い除け、新しいものと入れ替わること。 |
| 夜 | 一日の終わり、夜のこと。ここでは大晦日の夜を指します。 |
このように「除夜」は、単なる大晦日の夜ではなく、古い年から新しい年へと移り変わる、一年で最も特別な夜なのです。そんな神聖な夜に鳴らされるからこそ、「除夜の鐘」と呼ばれているのですね。
1.2 鐘の音に託す、一年の感謝と新たな年への願い
では、なぜその特別な夜に鐘を鳴らすのでしょうか。
お寺で鳴らされる鐘の音は、仏様の心が宿るとされ、その音色を聞くことで心が清められると考えられています。除夜の鐘には、この一年間に積もった私たちの罪や穢れ、そして心の迷いである「煩悩」を祓い清め、まっさらで清らかな心で新年を迎えるという大切な願いが込められているのです。
一年を振り返れば、嬉しかったこと、楽しかったことだけでなく、少し後悔していることや、誰かを傷つけてしまったことなど、心の澱(おり)となっている出来事もあるかもしれません。除夜の鐘の厳かな響きは、そんな私たちの心に静かに寄り添い、一年間のすべてを洗い流してくれます。
鐘の音に静かに耳を傾けながら、過ぎゆく年に感謝し、来る年が穏やかで幸多き一年になるよう願う。除夜の鐘は、私たちにとって、そんな心静かな時間を与えてくれる、日本の美しい伝統文化なのです。より詳しい仏教的な意味合いについては、曹洞宗の公式サイト「曹洞禅ネット」でも解説されていますので、ご興味のある方はご覧になってみてくださいね。
2. 除夜の鐘を108回つく深い意味 煩悩を祓う仏教の教え
大晦日の夜、どこからともなく聞こえてくる「ゴーン…」という厳かな鐘の音。この音を聞くと、新しい年がもうすぐそこまで来ていることを感じ、心が洗われるような気持ちになりますね。この除夜の鐘が、なぜ108回つかれるのか、ご存知でしょうか。その回数には、私たちの心と深く関わる仏教の教えが込められているのです。
除夜の鐘の108回という数は、人間が持つとされる「煩悩(ぼんのう)」の数を表しているといわれています。煩悩とは、私たちの心を悩ませ、かき乱す欲望や怒り、執着といった感情のこと。鐘を一つつくたびに、その煩悩が一つずつ取り除かれ、清らかな心で新年を迎えられるように、という願いが込められているのです。一年を静かに振り返りながら、鐘の音に耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。

2.1 人間の108の煩悩とは
「煩悩が108もあるなんて」と驚かれるかもしれませんね。仏教では、私たちの心の中にはそれだけ多くの迷いや苦しみの種があると考えられています。この108という数字の由来として最もよく知られているのが、「六根(ろっこん)」から生まれるという考え方です。
2.1.1 眼耳鼻舌身意から生まれる六根の働き
六根とは、仏教でいうところの6つの感覚器官のこと。具体的には、眼(見る)、耳(聞く)、鼻(嗅ぐ)、舌(味わう)、身(触れる)という五感に、それらを感じ取り判断する心である「意」を加えたものを指します。なんだか少し難しく聞こえますが、私たちが日々、物事を感じ取っている働きそのものですね。
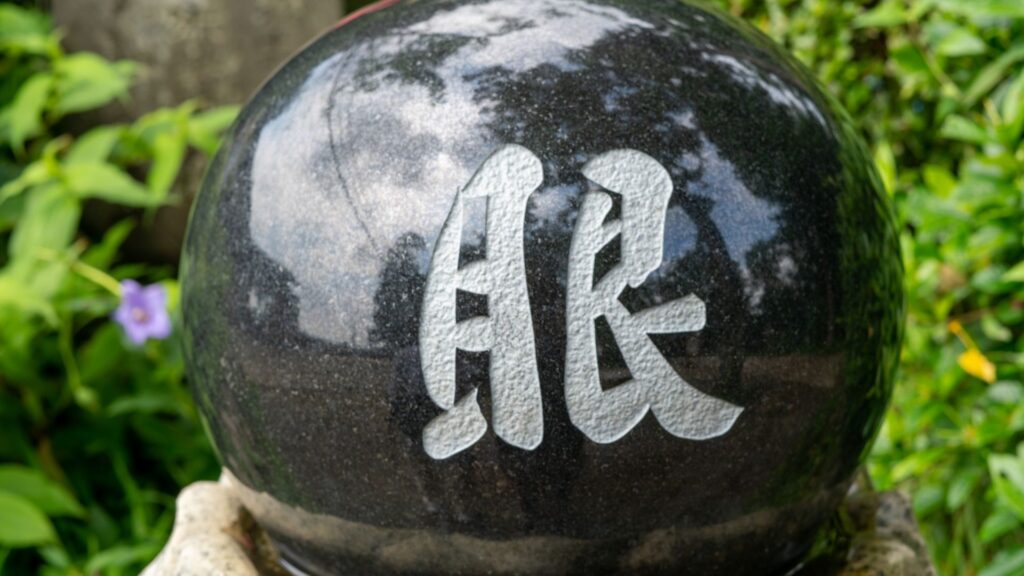
この六根が何かを感じ取るとき、私たちの心には「好(好き)」「悪(嫌い)」「平(どちらでもない)」という3つの感情が生まれます。例えば、美しい花を見て「好き」と感じたり、嫌な音を聞いて「嫌い」と感じたりすることです。
さらに、その感情にはそれぞれ「浄(清らかな状態)」と「染(汚れた状態)」の2種類があるとされています。つまり、六根から生まれる感情のパターンは、次のようになります。
6(六根) × 3(好き・嫌い・どちらでもない) × 2(清らか・汚れている) = 36種類
そして、この36種類の煩悩が、過去・現在・未来の「三世(さんぜ)」にわたって存在すると考えられているため、最終的に108の煩悩になると計算されるのです。
36種類 × 3(過去・現在・未来) = 108種類
この考え方を、下の表で少し整理してみましょう。
| 感覚 (六根) | 心の状態 | 性質 | 時間 (三世) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 眼・耳・鼻・舌・身・意 (6種類) | 好・悪・平 (3種類) | 浄・染 (2種類) | 過去・現在・未来 (3種類) | 108 |
こうして見ると、私たちの日常のささいな心の動きの一つひとつが、煩悩につながっていることがわかりますね。除夜の鐘は、そんな一年分の心の揺らぎを一つひとつ鎮めてくれる、大切な儀式なのです。
2.1.2 108以外の説も紹介
108という数字の由来は、実は一つだけではありません。ほかにもいくつかの興味深い説がありますので、ご紹介しますね。
- 四苦八苦(しくはっく)説
「四苦八苦する」という言葉は、普段の生活でも使いますよね。これは仏教に由来する言葉で、人間のあらゆる苦しみを表しています。この四苦八苦を数字に置き換えて、「4×9+8×9=108」とする説です。語呂合わせのようで、覚えやすいですね。 - 一年を表す説
一年間の季節の移り変わりを表す数字を足し合わせたもの、という説もあります。月の数の「12」、二十四節気の「24」、七十二候の「72」をすべて足すと、「12+24+72=108」となります。古い暦と結びついた、日本らしい考え方かもしれません。
どの説が正しいというわけではありませんが、いずれの説も、私たちが生きる上で感じる苦しみや、一年という時の流れを意識させてくれます。こうした様々な意味に思いを馳せながら鐘の音を聞くと、より一層感慨深い大晦日を過ごせるのではないでしょうか。
3. 除夜の鐘の歴史と由来 いつどこで始まった?
大晦日の夜、どこからともなく聞こえてくるゴーンという厳かな鐘の音。日本の冬の風物詩として、私たちの心に深く刻まれていますよね。でも、この「除夜の鐘」の習慣は、いつ、どこで始まったものなのでしょうか。その歴史をたどると、意外なルーツが見えてきますよ。
3.1 起源は中国から 禅宗のお寺の習慣
実は、除夜の鐘の起源は、お隣の中国、宋の時代(960年~1279年)にまでさかのぼります。当時の禅宗のお寺では、人々に時刻を知らせるため、朝と夕方に鐘をつく習慣がありました。
その中でも、一年の終わりである大晦日の夜につく鐘は特別なもの。古い年を送り、新しい年を迎えるという節目の合図として、大切にされていたのです。この習慣が、日本に禅宗が伝わるのと一緒に、海を渡ってやってきました。曹洞宗の公式サイトにも、この習慣が中国の宋代の禅林で定められた作法に由来することが記されています。(参考:曹洞宗公式サイト 曹洞禅ネット)
3.2 日本に除夜の鐘が広まった時代
日本に伝わった当初、鐘をつく習慣は禅宗のお寺だけの特別な行いでした。それが、私たちの暮らしに身近なものになったのは、もう少し後の時代のことです。その広まりの歴史を、少し覗いてみましょう。
| 時代 | 主な出来事と特徴 |
|---|---|
| 鎌倉時代~室町時代 | 中国から禅宗と共に鐘をつく習慣が伝来しました。この頃はまだ、一部の禅寺で行われるのみでした。 |
| 江戸時代 | 庶民の間にも除夜の鐘の習慣が広まり始めました。お寺が人々の暮らしの中心にあった時代、大晦日の鐘の音は、町の人々にとって一年の終わりを告げる大切な音色となっていったのです。 |
| 明治時代以降 | 神道と仏教がはっきりと分けられた後も、除夜の鐘は仏教行事として、また日本の文化として定着。全国のお寺で大晦日の夜に鐘がつかれるようになり、現在のような国民的な年末の風物詩となりました。 |
このように、もともとは中国のお寺の作法だった除夜の鐘は、長い年月をかけて日本の文化に溶け込み、多くの人々に親しまれる大晦日の大切な習慣へと姿を変えていったのですね。
4. 除夜の鐘はいつから何回つく?時間と回数のルール
大晦日の夜、どこからともなく聞こえてくるゴーンという厳かな鐘の音。一年の終わりを告げる除夜の鐘は、私たちの心を静かに整えてくれる特別な響きを持っていますね。この鐘の音を聞くと、「ああ、今年ももうすぐ終わるのだな」と、しみじみと感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、多くの人が意外と知らない除夜の鐘の時間や回数にまつわるルールについて、やさしく紐解いていきます。

4.1 除夜の鐘を叩き始める時間帯
除夜の鐘は、一般的に大晦日の夜、年が変わる少し前からつき始められます。具体的には、午後11時頃から準備が始まり、午後11時45分頃からつき始めるお寺が多いようです。
もちろん、これはあくまで目安。お寺によっては、もっと早い時間からつき始めるところや、深夜0時ちょうどから始めるところなど様々です。もしご近所のお寺で鐘つきに参加してみたいとお考えでしたら、事前に時間を確かめておくと安心ですね。静寂に包まれた大晦日の夜、厳かな鐘の音が響き渡る光景は、きっと心に残る体験になることでしょう。
4.2 108回のうちわけ 年をまたいでつく意味
除夜の鐘が108回つかれることはよく知られていますが、そのつき方には、実は奥深い意味が込められた2つの主なパターンがあります。どちらのつき方にも、新しい年を晴れやかな気持ちで迎えるための祈りが込められています。
お寺の宗派や考え方によって、つき方は異なりますが、代表的な2つのパターンを表にまとめてみました。
| つき方のパターン | 旧年中(12月31日) | 新年(1月1日) | 込められた意味 |
|---|---|---|---|
| 年をまたいでつく | 107回 | 最後の1回 | 旧年のうちに煩悩を祓い、新年は煩悩に惑わされないようにと願う。 |
| 年内にすべてつく | 108回 | 0回 | 旧年のうちに全ての煩悩を祓い清め、清浄な心で新年を迎える。 |
最も広く知られているのは、年内に107回をつき、年が明けた瞬間に最後の1回をつくという方法です。これは、曹洞宗の公式サイト「曹洞禅ネット」でも紹介されているつき方で、過ぎ去った一年の煩悩を祓い、新しい年には煩悩に悩まされることのないようにという願いが込められています。
一年の終わりに鐘の音に静かに耳を澄ませば、過ぎ去った日々の様々な出来事が心によみがえり、新たな年への希望がそっと湧いてくるようですね。この鐘の音は、私たちにとって一年を締めくくる大切な心の節目なのかもしれません。
5. 一般人も除夜の鐘はつける?参加方法と知っておきたいマナー
大晦日の夜、厳かに鳴り響く除夜の鐘。テレビの向こうの出来事と思いがちですが、実は私たち一般の人が参加できるお寺もたくさんあるのですよ。一年の締めくくりに自らの手で鐘をつき、心穏やかに新年を迎える時間は、きっと忘れられない思い出になるはずです。ここでは、除夜の鐘つきに参加するための方法や、知っておきたい服装、作法について、やさしくご紹介しますね。
5.1 除夜の鐘がつけるお寺の探し方
「近所で鐘つきができるお寺はあるかしら?」と思ったら、まずは情報を集めてみましょう。探し方にはいくつかの方法があります。
一番手軽なのは、インターネットで調べる方法です。「お住まいの地域名 除夜の鐘 一般参加」や「〇〇市 除夜の鐘 整理券」といった言葉で検索すると、地域の情報サイトやお寺の公式サイトが見つかることがあります。また、各自治体や観光協会のウェブサイトでも、年末年始のイベント情報として紹介されていることが多いですよ。
気になるお寺が見つかったら、必ず事前に電話などで詳細を確認しましょう。特に、次の点は確かめておくと安心です。
- 一般参加が可能かどうか
- 整理券が必要かどうか(配布時間や場所も)
- 鐘をつき始める時間
- 参加費(志納金)の有無
- 駐車場の有無
人気のお寺では、早い時間に整理券の配布が終了してしまうこともあります。年末は何かと忙しい時期ですが、少し早めに計画を立てて、ゆとりをもって準備を進めたいですね。
5.2 鐘をつくときの服装や作法
初めて鐘つきに参加するときは、どんな服装で行けば良いのか、作法はあるのか、少し緊張しますよね。でも、心配いりません。大切なのは、仏様への敬意と、周りの方への配慮の気持ちです。
5.2.1 ふさわしい服装と持ち物
大晦日の夜は、想像以上に冷え込みます。一番大切なのは、しっかりとした防寒対策です。暖かいコートはもちろん、マフラーや手袋、帽子、カイロなども忘れずに準備しましょう。足元は、境内が暗かったり、砂利道だったりすることもあるため、歩きやすく滑りにくい靴がおすすめです。ヒールのある靴は避けた方が安全ですよ。
また、お寺は神聖な場所ですので、あまり華美な服装は避け、落ち着いた色合いの服装を心がけると良いでしょう。
| 持ち物 | ポイント |
|---|---|
| 防寒具 | コート、マフラー、手袋、帽子、カイロなど。重ね着できるものが便利です。 |
| 志納金(お布施) | お気持ちを納めるため、小銭やポチ袋を準備しておくとスマートです。 |
| 整理券 | 必要な場合は、忘れないようにしましょう。 |
| 懐中電灯 | 足元が暗い場合に備えておくと安心です。 |
5.2.2 鐘をつくときの作法
お寺によって細かい違いはありますが、基本的な作法は次の通りです。難しく考えず、心を込めて丁寧に行いましょう。
- 順番を待つ
列に並び、静かに自分の順番を待ちます。前の人が鐘をついている間は、心を落ち着けて音色に耳を澄ませてみましょう。 - 鐘の前で合掌・一礼
自分の番が来たら、鐘(梵鐘)に向かって進み、静かに手を合わせて一礼します。 - 鐘をつく
綱(撞木(しゅもく)を動かすための綱)を両手で持ち、力いっぱい引くのではなく、綱の重みを感じながらゆっくりと後ろに引き、自然に鐘に当たるようにします。ゴーンという余韻を心で感じながら、一つ、煩悩が消えていく様子を思い浮かべてみてください。 - つき終わったら合掌・一礼
鐘をつき終えたら、再び鐘に向かって静かに合掌し、一礼してからその場を離れます。
この一連の動作に、一年間の感謝と、新しい年への願いを込めてみてはいかがでしょうか。澄み渡る冬の夜空に響く鐘の音は、きっとあなたの心を清々しい気持ちで満たしてくれることでしょう。
6. 【エリア別】除夜の鐘で有名なお寺を紹介
除夜の鐘の意味や歴史を知ると、実際にその厳かな音色を間近で聴いてみたくなりますよね。年の瀬の澄んだ夜空に響き渡る鐘の音は、一年の締めくくりにふさわしい特別な体験です。ここでは、全国各地で除夜の鐘が有名なお寺をいくつかご紹介します。新しい年を迎える大切なひとときをどこで過ごそうか、思いを巡らせてみませんか。
ご紹介する情報は例年のものであり、年によっては変更される場合があります。お出かけの際は、必ず各お寺の公式サイトなどで最新の情報をご確認くださいね。
6.1 関東地方で除夜の鐘が有名なお寺

都心から少し足を伸ばすだけで、歴史あるお寺の荘厳な鐘の音に触れることができます。初詣とあわせて訪れるのも素敵ですね。
| お寺 | 特徴 | 一般参加について |
|---|---|---|
| 増上寺(東京都港区) | 徳川将軍家とゆかりの深いお寺です。テレビ中継でもおなじみの、迫力ある鐘つきを見学できます。東京タワーを背景に響く鐘の音は、都会ならではの美しい情景です。 | 一般の方も鐘をつくことができますが、例年、早い時間から配布される整理券が必要です。希望される方は、事前に配布時間などを確認しておくと安心です。詳しくは増上寺 公式サイトをご確認ください。 |
| 浅草寺(東京都台東区) | 東京を代表する観光地でもある浅草寺。「花の雲 鐘は上野か 浅草か」と松尾芭蕉の句にも詠まれた「時の鐘」が有名です。多くの人で賑わう中、新年を迎える活気を感じられます。 | 「時の鐘」は一般の方はつけませんが、境内にある弁天山の鐘を、「つく権利」の事前申し込みに当選した方がつくことができます。申し込み方法は公式サイトで告知されます。 |
| 長谷寺(神奈川県鎌倉市) | 「長谷観音」として親しまれ、四季折々の花々が美しいお寺です。鎌倉の静かな夜に響く鐘の音は、心を穏やかにしてくれます。 | 例年、人数限定で一般の方も鐘をつくことができます。事前に整理券が配布されることが多いので、早めに訪れるのがおすすめです。詳細は長谷寺 公式サイトでご確認ください。 |
6.2 関西地方で除夜の鐘が有名なお寺

古都の風情が漂う関西には、国宝級の梵鐘を持つお寺が数多くあります。その歴史の重みを感じながら、心静かに新年を迎えたい方にぴったりです。
| お寺 | 特徴 | 一般参加について |
|---|---|---|
| 知恩院(京都府京都市) | 日本三大梵鐘のひとつに数えられる、重さ約70トンもの巨大な大梵鐘で知られています。僧侶たちが「えーい、ひとつ」「そーれ」の掛け声とともに、力を合わせて鐘を撞く様子は圧巻の一言です。 | 一般の方は鐘をつくことはできませんが、その迫力ある鐘つきの様子を間近で見学できます。毎年多くの見学者が訪れるため、早めの時間に行くことをお勧めします。詳しくは知恩院 公式サイトでご確認ください。 |
| 東大寺(奈良県奈良市) | 大仏さまで有名な東大寺の梵鐘は、重さ約26.3トンもある国宝です。「奈良太郎」の愛称で親しまれ、その音色は深く、長く響き渡ります。 | こちらも一般の方は鐘をつくことはできませんが、厳かな雰囲気の中で行われる鐘つきを見学できます。大仏殿の夜間無料拝観とあわせて訪れる方が多いです。 |
| 四天王寺(大阪府大阪市) | 聖徳太子が建立した日本仏法最初の官寺。大阪の中心地にありながら、静かで落ち着いた時間が流れています。北鐘堂、南鐘堂、太鼓楼の3つの鐘が鳴らされます。 | 例年、整理券を受け取った方が鐘をつくことができます。都会の真ん中で迎える新年は、また格別な趣があります。詳細は四天王寺 公式サイトをご確認ください。 |
6.3 全国各地の特色ある除夜の鐘

北から南まで、日本各地にはその土地ならではの歴史や文化を映す除夜の鐘があります。旅先で新年を迎える際の楽しみのひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
| お寺 | 特徴 | 一般参加について |
|---|---|---|
| 永平寺(福井県) | 曹洞宗の大本山として知られる禅の道場です。山深い静寂の中に響き渡る鐘の音は、聴く人の心を洗い清めるような荘厳さがあります。 | 一般の方も鐘をつくことができます。修行僧たちの厳しい生活に思いを馳せながらつく鐘は、特別な体験となるでしょう。詳しくは永平寺 公式サイトでご確認ください。 |
| 善光寺(長野県) | 「牛に引かれて善光寺参り」で知られる無宗派の古刹です。日本最古の梵鐘といわれる重要文化財の鐘の音を聴きながら、多くの参拝者とともに新年を迎えます。 | 例年、先着108組が鐘をつくことができます。整理券は早い時間に配布が終了することが多いので、希望される方は事前の情報収集が欠かせません。 |
| 観世音寺(福岡県太宰府市) | 国宝に指定されている、日本最古級の梵鐘があることで有名です。菅原道真公も聴いたかもしれないといわれるその音色は、悠久の歴史を感じさせてくれます。 | 一般の方も鐘をつくことができます。歴史の重みを感じながら、心静かに新年を迎えたい方におすすめです。 |
お住まいの地域や旅先で、心に残る除夜の鐘の音に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。きっと、清々しい気持ちで新しい一年をスタートできるはずです。
7. 近年の除夜の鐘をめぐる事情と新しい動き
古くから日本の大晦日の夜に鳴り響いてきた除夜の鐘。その厳かな音色に、一年の終わりと新しい年の始まりを感じる方も多いことでしょう。しかし近年、私たちの暮らしの変化とともに、この伝統的な風物詩にも新しい動きが見られるようになりました。ここでは、現代における除夜の鐘の事情について、少しだけ耳を傾けてみましょう。
7.1 騒音問題による中止や時間変更の動き
近年、ニュースなどで耳にする機会が増えたのが、除夜の鐘の「騒音問題」です。かつては静かだったお寺の周辺にも住宅が増え、人々の暮らし方もさまざまになりました。夜遅くに響く鐘の音を「風情がある」と感じる人がいる一方で、「音が大きくて眠れない」といった苦情が寄せられるケースが、残念ながら一部で出てきているのです。
こうした声を受けて、大晦日の夜に鐘をつくことを中止したり、時間を早めてお昼の時間帯に実施したりするお寺が少しずつ増えています。静岡県牧之原市にある大澤寺では、住民への配慮から2015年より昼間に鐘をつく「除夕の鐘(じょせきのかね)」へと変更したことが話題となりました。
もちろん、伝統文化を守りたいと願う声も多く、お寺の方々も苦慮されています。地域の方々と話し合いを重ねながら、皆が心地よく新年を迎えられる方法を模索しているのが現状です。もし近所のお寺の鐘が聞こえなくなったと感じたら、こうした背景があるのかもしれませんね。
7.2 多様化する大晦日の鐘のつき方
社会の変化に対応しながら、大切な伝統を未来へつないでいこうと、各所でさまざまな工夫が生まれています。これまでとは少し違った、新しい除夜の鐘の楽しみ方が広がっているのですよ。
代表的な新しい取り組みをいくつかご紹介します。
| 新しい鐘のつき方 | どのようなもの? |
|---|---|
| 昼間の鐘(除夕の鐘) | 大晦日の日中に鐘をつきます。夜間の騒音に配慮できるだけでなく、お子様連れの家族やご年配の方も参加しやすいのが魅力です。明るい時間帯に、清々しい気持ちで一年を締めくくれます。 |
| オンライン配信 | YouTubeなどの動画サイトを利用して、除夜の鐘の様子をライブ配信するお寺が増えています。自宅にいながら、全国の有名なお寺の鐘の音を聞くことができます。寝室で静かに耳を傾けるのも、素敵な過ごし方ですね。 |
| アプリやスマートスピーカー | スマートフォンのアプリや、スマートスピーカーに「除夜の鐘を鳴らして」と話しかけることで、鐘の音を再生できるサービスも登場しています。好きな時間に、手軽に大晦日の雰囲気を味わえるのが嬉しいポイントです。 |
こうした新しい動きは、時代に合わせて伝統文化を未来へつないでいこうとする、お寺の皆さんの温かい想いの表れなのかもしれません。昔ながらの風情を大切にしつつ、現代の暮らしに寄り添った形で、除夜の鐘はこれからも私たちの心に響き続けていくことでしょう。
8. 除夜の鐘の意味に関するよくある質問
年の瀬に聞こえてくる除夜の鐘の音は、日本の大晦日の象徴的な風景ですよね。ここでは、そんな除夜の鐘にまつわる、ふとした疑問にお答えします。知っているようで意外と知らない豆知識で、新しい年をより深く味わってみませんか。
8.1 除夜の鐘と初詣の関係は?
大晦日に除夜の鐘をつき、年が明けると初詣へ。この一連の流れを毎年の習慣にされている方も多いのではないでしょうか。この二つは、実は由来が異なります。
除夜の鐘は仏教の行事でお寺にて行われ、一方の初詣は主に神道の習慣で神社にて行われます(お寺へ初詣に行くこともあります)。除夜の鐘で108の煩悩を祓い、清らかな心になった状態で、新しい年の幸せを神様や仏様にお祈りしに行く、という流れが自然に定着したのですね。
大晦日の夜から元旦にかけてお参りする「二年参り」という習慣も、この二つの行事が深く結びついていることを示しています。除夜の鐘をついたお寺で、そのまま新年のご挨拶(初詣)をすることもできますよ。古い年を送り、清らかな心で新しい年を迎えるという点で、由来は違えど、私たちの心の中では深くつながっている大切な習慣といえるでしょう。
8.2 自宅で除夜の鐘を楽しむ方法
「近所にお寺がない」「寒さや夜の外出は少し大変…」そんなときでも、ご自宅で除夜の鐘の風情を味わう方法がいくつかあります。ご自身のライフスタイルに合わせて、静かな年越しの時間を過ごすのも素敵ですね。
ご自宅にいながらでも、厳かで心安らぐ鐘の音に耳を傾けることができます。一年を静かに振り返り、新たな気持ちで新年を迎える準備をしてみてはいかがでしょうか。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| テレビ・ラジオ番組 | NHKの「ゆく年くる年」をはじめ、多くの局で全国各地のお寺から鐘の音が生中継されます。映像と共に、日本の年越しの雰囲気を存分に味わえます。 |
| インターネットの動画配信 | YouTubeなどでは、有名なお寺が除夜の鐘の様子をライブ配信することが増えています。好きな場所の鐘の音を、好きなタイミングで聴くことができます。 |
| スマートフォンのアプリ | 除夜の鐘をテーマにしたアプリも登場しています。画面をタップして鐘をつく体験ができ、手軽に年越しの気分を楽しめます。 |
| CDや音楽配信サービス | 除夜の鐘の音を収録した音源もあります。ヒーリングミュージックとして、リラックスしながら一年を振り返る時間のお供にもぴったりです。 |
ご自身のペースで、静かに一年を振り返る時間を持つのもまた、乙なもの。温かいお部屋で鐘の音に耳を澄ませば、心が洗われるような穏やかな気持ちで、新年を迎えられることでしょう。
9. まとめ
大晦日の夜に響き渡る除夜の鐘。その音色には、私たちを悩ませる108の煩悩を祓い、清らかな心で新年を迎えるという、仏教の深い教えが込められていたのですね。中国から伝わった歴史ある習慣ですが、近年は騒音問題などから形を変えつつも、大切に受け継がれています。今年は鐘の音に静かに耳を傾け、ゆく年に感謝し、新しい年への願いを込めてみてはいかがでしょうか。厳かな響きが、あなたの毎日に穏やかな光を添えてくれますように。










コメント